起業や持続的な会社経営をするためには、まとまった資金が必要です。資金調達にはさまざまな方法があり、融資や自己資金、クラウドファンディングなどをイメージされる方が多いかもしれません。しかし近年、暗号資産の発行を通じて資金調達をおこなうWeb3事業者が増えており、新たな方法として注目を集めています。
この記事では、Web3関連事業で資金調達を検討している方に向けて、暗号資産発行による資金調達の方法や注意点、そのほかのWeb3に関連する資金調達方法について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
目次
暗号資産を発行して資金調達を行う方法
自己資金以外で資金調達するには、さまざまな方法があります。銀行融資や株式の発行を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、暗号資産の発行による資金調達も可能です。
暗号資産で資金を得る方法は、株式を発行する場合と仕組みが似ています。異なるのは発行するのが株式か暗号資産かのみで、企業が発行し、それを投資家に購入してもらうことで資金を集める点は同じです。ここでは、暗号資産を発行して資金調達する具体例を紹介します。
IEO
IEO(Initial Exchange Offering)は、暗号資産を用いて資金調達する方法のひとつで、取引所が、暗号資産を発行する企業と投資家の間に入るのが特徴です。取引所が企業の業績やプロジェクト内容などを調査し、審査を通過した場合のみIEOが実施されるため、投資家に安心感を与えられます。
一方で、IEOの審査を通過するのは簡単ではありません。プロジェクト内容が浅はかであったり、経営状況が悪かったりすると、そもそも審査を通過せず資金調達できない可能性もあります。
国内でIEOが実施された事例として挙げられるのが、Coincheck(コインチェック)のブリリアンクリプトトークンです。購入申し込みが殺到し、話題になりました。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000125018.html
ICO・IDO
ICO(Initial Coin Offering)は、企業などが独自の暗号資産を発行して投資家に販売する方法です。IEOとは違って仲介者がおらず厳しい審査もないため、簡単に手続きができます。また、地域の限定がなく、世界中から資金調達できるのもメリットです。いっぽうで、IEOと比較してプロジェクトの信憑性が低いとみなされ、出資者が現れるかわからないデメリットもあります。
IDO(Initial DEX Offering)は、企業が新しく発行した暗号資産をDEXで公開し、投資家に購入してもらう方法です。DEXとは、特定の管理者が存在しない取引所のことで、ブロックチェーンを活用して自動で取引をおこないます。仲介者がいないため、IEOと比べるとコストがかからないのがメリットです。ですが、DEXは2020年頃から台頭してきた比較的新しい概念であるため、投資家に認知されていない可能性があります。
DAOでガバナンストークンを販売
DAO(Decentralized Autonomous Organization)とは、特定の管理者を置かず、参加者全員がプロジェクトや事業の運営の意思決定に携われる組織のことです。プロジェクトリーダーや会社のトップが意思決定を行う従来の組織とは異なり、参加者の投票で運営方針を決められるため、新たな組織の形として注目を集めています。
ガバナンストークンはDAOで発行される暗号資産の一種で、投資家はこれを購入すれば組織の意思決定への参加権が得られる仕組みです。DAOでおこなわれる取引はすべてブロックチェーンを用いているため、高速で効率的に資金調達ができます。
暗号資産を発行して資金調達を行う注意点
近年Web3の成長に伴い、暗号資産を活用した資金調達の事例が増えてきています。しかし、まだまだ課題が多く残っており、法制度や環境整備は発展途上です。
この章では、暗号資産を用いて資金調達するときの注意点をふたつ紹介します
会計や税務が複雑になる
自社発行した暗号資産をDeFiなどで利用する場合、ブロックチェーンやスマートコントラクトの特性上、自動的に取引が行われるため、会計処理や税務対応が非常に複雑になります。
また、自社発行の暗号資産を用いて資金調達を行った場合、期末時価評価課税に関して令和6年に税制改正が行われましたが、「他者に移転できないよう技術的措置が取られていること」が条件です。この技術的措置が取られていない場合、引き続き期末時価評価の対象となります。
そのため、DeFiなどで自社発行の暗号資産を動かす際には、これらの条件を十分に確認し、複雑な会計処理や税務対応が求められます。
資金決済法などによる規制を受ける可能性がある
資金決済法では、暗号資産の売買や交換を事業者としておこなう場合に、内閣総理大臣の承認を得なければならないと定められています。そのため、暗号資産の売買や交換を事業として行う場合、登録を受けずに営業すると無登録業者として違法行為となり、罰則が科される可能性があります。
また、単発的な売買は事業には該当しませんが、反復継続して利益を得る目的の取引は事業とみなされる場合があります。そのため、どの行為が事業に該当するかを正確に理解することが重要です。
VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受ける
VCとは、ベンチャー企業やスタートアップ企業など将来性が期待できる企業に投資する会社や組織のことです。投資家たちは初期にこれらの企業の株を買い、上場や急成長を遂げたタイミングで、株を売却しキャピタルゲインを獲得します。事業者は、初期段階からまとまった資金が得られることにくわえてVCの経営ノウハウを活用できるため、事業を急速に成長させられるのが大きなメリットです。
出資を受けたいときは、VCにピッチを送りましょう。ピッチとは、自身のビジネスアイデアやサービスを投資家にアピールする短時間のプレゼンテーションです。ほかにも、投資家に直接出会ったり、ビジネスコンテストに参加したりする方法があります。
著名なWeb3系のVC
VCには金融機関系や海外系、大学系など多くの種類があり、特徴や運営方法はさまざまです。ここでは、著名なWeb3系のVCを紹介します。
Binance Labs
Binance Labs(バイナンスラボ)は、ブロックチェーンを活用する事業に投資するVCです。大手暗号資産取引所のバイナンスから誕生し、現在は独立して暗号資産やNFT関連の事業を扱っています。審査が厳しいと言われており、見込みのあるプロジェクトを厳選して出資しているようです。
なお、2025年1月23日にブランド名を「YZi Labs(YZiラボ)」に変更したと発表されました。今後はブロックチェーン事業だけでなく、AIやバイオテクノロジー事業にも投資していくとのことです。
A16Z
A16Z(アンドリーセン・ホロウィッツ)は、シリコンバレーを拠点にWeb3や暗号資産、テクノロジー分野に投資するVCです。これまでに世界最大のSNSであるFacebookや民宿施設管理者と利用希望者をつなぐAirbnb(エアビ)などのグローバル企業から、大手暗号資産取引所のCoinbase(コインベース)などのブロックチェーン事業まで幅広く支援をおこなっています。
発行体や財団から助成金(Grant)を得る
暗号資産やブロックチェーンの発行体やそれに近い財団は、ブロックチェーンのエコシステムを発展させる目的で、助成プログラムを設定している場合があります。たとえばイーサリアムでは、イーサリアム財団が助成プログラム提供しており、さまざまサポートを利用できます。
このようなプログラムは、少額の対応をしている場合が多く、助成を受けるハードルは低いです。イーサリアム財団は、30,000ドル(約450万円・1ドル=150円)以下の助成金であれば申請後約 2 週間で助成可否の決定が下されるとしており、小規模チームでも活用できるようになっています。
参考:イーサリアム財団
まとめ
資金調達にはさまざまな方法がありますが、なかでもWeb3事業者に注目されているのが暗号資産の発行による資金調達です。独自の暗号資産を発行し、投資家に買ってもらうことで資金が得られます。これ以外にも、VCや暗号資産の発行体、または財団から助成を受けることも可能です。今後さらにWeb3が推進され、Web3を活用したサービスやシステムが増えていくでしょう。まだまだ暗号資産を用いた資金調達の事例は少ないですが、これからメジャーになっていくかもしれません。
最近では、暗号資産を担保に融資を受ける暗号資産担保型のローンを提供する、デジタルアセット担保ローンもあります。なお、デジタルアセット担保ローンは大和証券グループ本社とクレディセゾンの合弁会社であるFintertech株式会社が提供しています。
暗号資産を担保で融資を受ける場合、暗号資産は利益確定(利確)を行わなくても良いといったメリットが存在するため、税制的なメリットを受けられる可能性があります。

暗号資産をもとに資金調達を行いたい場合などに活用できるため、ご検討ください。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- 「IEOを実施して暗号資産を用いた資金調達を行いたい」
- 「新規の暗号資産を発行した資金調達を専門家に相談したい」
など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

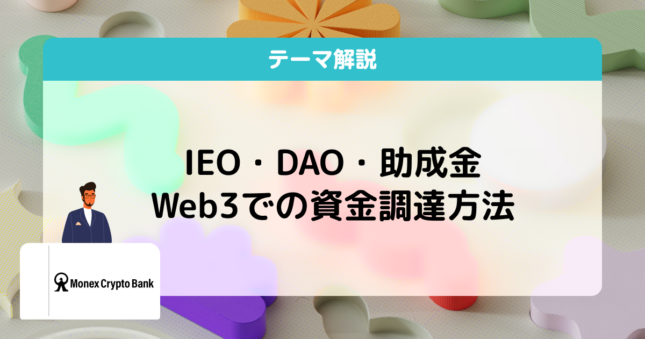

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




