Metaが社名を変更し大規模投資を行うなど、一時期大きな注目を集めたメタバース。
しかし2023年現在、想定されていたような爆発的な普及には至っておらず、「メタバースは失敗だったのでは?」という声も聞かれます。
本記事では、メタバースが広く普及しない理由を分析するとともに、テクノロジーの進化に伴う今後の可能性や、私たちの生活や働き方にもたらす変化について解説します。
メタバースとは?
「メタバース」という言葉の定義は総務省が取りまとめた資料で示されています。
参照:総務省「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」 中間とりまとめ
ユーザー間で「コミュニケーション」が可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる、仮想的なデジタル空間・仮想空間とのことで、以下の要素を主軸とします。
- 臨場感・再現性
- 自己投射性・没入感
- インタラクティブ
- オープン性
そのようなコンセプトのデジタルエンタテインメントとしては、以前からオンラインゲームという形で一般化されていました。あえてメタバースと呼ぶ場合、そういったオンラインゲームとは差別化する意図が盛り込まれる場合があります。
一方で、視聴覚の没入感を重視したオンラインゲーム=メタバースと捉えることもできます。
単一のゲームメーカーの提供作品ではなく、行政やマスメディア・広告代理店をはじめとする企業がプロジェクトとして制作・提供しているもの。特定の遊びを提供しないもの。ただし近年のオンラインゲームでは「オープンワールド」と呼ばれる世界のみ提供して「遊び方」はプレイヤーに委ねる形式の作品も多く、メタバースと明確に定義を分けることが難しい場合もあります。
VRゴーグルなどのデバイスを用いてより強い没入感を得るもの。一方で「スマホで簡単にアクセスできるメタバース」を謳うプロジェクトもあり、これもまた定義としては曖昧です。
メタバースが「普及しない」「意味がない」と言われる理由
ここからはメタバースが普及しない理由・意味がないと言われる理由を解説していきます。
セカンドライフの失敗のイメージ
セカンドライフは2003年にリリースされたメタバースの先駆け的なサービスです。セカンドライフが失敗した大きな理由として、当時のパソコンのスペックでは十分な動作ができなかったことが挙げられます。
また、具体的な価値提案が不明確で、「何となく面白そう」という漠然としたイメージだけが先行し、明確なユースケースを示せなかったことが失敗の主な要因とも考えられています。
VRデバイス・HMDが一般層にとっては高額
メタバースへの没入の為にぜひ利用したいのが、VRデバイス・HMD(ヘッドマウントディスプレイ)といった専用機器です。
しかし、これらの機器は一般層にとっては高額である上に、まだ具体的な面白さが提示されていないメタバースに利用するには敷居が高いといえる状況です。
現状では、広く普及をはかっているサービスほど「スマホから簡単にアクセスできる」など、専用機器を求められない方向での訴求が行われています。
通信速度や遅延等の技術的制約
メタバース空間は3Dの画像処理やリアルタイムでのコミュニケーションなど、通信の遅延がサービスを楽しむ上でのストレスとなっていきます。
せっかく試してみようと思ったメタバース空間が遅延ばかりのカクカクな動き、まともに会話が成立しないといった状況ではユーザーは離れてしまいます。
かつてのセカンドライフがそのような快適性の欠落によって失敗した例に学び、新たに迎え入れるユーザーにストレスフリーなサービスを提供するクオリティ確保が求められます。
仮想空間への抵抗感
現在のSNS利用では、顔を出してのオープンなコミュニケーションが主流となりつつあります。アバターを通して匿名で仮想空間を利用するという形式は、ハンドルネーム(仮名)でインターネットを利用した経験がある一部の世代や、ゲームユーザー以外ではあまり馴染みがありません。
そういった仮想空間への抵抗感から、メタバースに魅力を感じないとする層が存在します。
Metaの失敗
Facebookの創始者であるマーク・ザッカーバーグ氏は、自身の会社を「Meta」に改名しメタバース関連事業に注力する方針を打ち出しました。しかし、Meta社が仕掛けたメタバース事業は2022から2023年ごろに「失敗」の評価が聞かれるようになっています。
自社制作のVRゲーム『Horizon Worlds(ホライゾン・ワールド)』がバグの多さによるクオリティ不足・人気不足に陥ったほか、周辺機器の製造・販売でも大きな赤字を生んでしまいました。
これらの「失敗」には、マーク氏の思い付きとも取れる唐突な発案や、それに対する従業員の不満・モチベーションの低下も原因の多くを占めています。
メタバースには明るいニュースも出てきている
メタバースはまだその魅力が十分にアピールできておらず、普及しない・意味がないという評価を下されてしまいがちです。しかし、メタバース関連には明るいニュースも出てきています。
ここからはメタバースに関連するポジティブな話題を解説していきます。
AppleやMetaなどの参入
メタバースにはAppleやMetaなど、アメリカのIT最大手の参入が相次いでおり、技術やサービスのブラッシュアップが期待されます。
Meta社の失敗事例については前項で解説していますが、資本のある企業参入を試みているということは、業界の可能性が期待されていると言える状況です。
AppleからはApple Vision Proなどの機材が発売されています。Apple Vision Proはメタバース用のVR(バーチャルリアリティ)ゴーグルとして使用するほかに、現実の風景に情報を投影するAR(アグメンティッド・リアリティ)機器として仕事の作業に使ったり、動画や音楽を楽しむ用途も提案されています。
Apple Vision Proの販売価格は非常に高額ですが、こういったコンセプトのデバイスが普及し低価格化していけば気軽にVRを楽しむことができるでしょう。
VRデバイス・HMDの廉価化
VRデバイスについては、スマホの登場で小型高解像度ディスプレイが大量生産され、比較的安価に生産することができました。
また、視界を覆うカバーにスマホをはめ込むことで、簡易的なVRゴーグルとして使用できるグッズも販売されています。より高性能なVRゴーグルやHMDの方がもちろんクオリティは上ですが、まずは多くの人に「触れてもらう」ことがメタバースの普及には不可欠です。
Web3への注目の高さ
メタバースはWeb3と同時に発展が期待されています。Web3技術であるブロックチェーンやスマートコントラクトを用いることで、メタバース内で経済活動を行えるようになるため、メタバースがゲームだけにとどまらない発展ができると期待されているためです。
メタバースプラットフォームである「The Sandbox」では、マネックスグループが開発した2035年の近未来都市をコンセプトとしたOASISが構築されました。「The Sandbox」上ではイベントや施設などを構築し、入場料や参加費を取るといった経済活動を行うことも可能です。
OASISでは、美術館やステージなどを構築し、アーティストなどとのコラボを行っています。
若年層ユーザーの増加
一定の年齢層以上には、デジタルゲームやインターネットに対する苦手意識や偏見が存在しています。
一方でデジタルネイティブと呼ばれる若年層にとっては、デジタルゲームは幼い頃から慣れ親しんだ遊びであり、一般的なコミュニケーションツールでもあります。また、イラストや3Dモデリングで作成したアバターをまとって実際の人間がパフォーマンスをするVtuberといった存在も一般化してきています。
若年層ユーザーの増加により、セカンドライフなどの過去の失敗例でネガティブな印象を持たれているメタバースにも新たな顧客が生まれてきています。
ただし、若年層は「コンテンツが楽しいか」「時間を割くのに値するか」という評価が非常にシビアでもあります。セカンドライフのように「何となく凄い場所」という曖昧なコンセプトのまま魅力を提供できなかったとしたら、今度こそメタバースは商業的な低評価から脱することができなくなるかもしれません。
今後のメタバースの将来性と社会変化について
技術的な問題、ユーザーの心理的な障壁など、メタバースにとってネガティブな要素はまだまだ山積みです。一方でこれらの問題点も社会変化によって緩和・改善が見られるようになってきました。
ここからは今後のメタバースの発展に伴う社会変化について解説していきます。
参考:総務省「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」 中間とりまとめ
通信環境の改善
インターネット通信環境は、データ転送技術の革新と通信インフラの整備により、過去20年で驚異的な進化を遂げました。2000年代初頭、携帯電話でのインターネット利用では一枚の写真をダウンロードするのに数分を要していましたが、現在では高画質の動画ストリーミングさえも、場所を問わずスムーズに楽しむことができます。
特筆すべきは、この高度な通信環境が一般ユーザーにも手の届く価格で提供されている点です。かつては企業や研究機関でしか実現できなかった高速大容量通信が、現在では日常的なサービスとして広く普及しています。
通信技術の発展は今後も続くと予測されています。通信事業者や政府機関による将来予測では、次世代のデジタルコンテンツやサービスを支える基盤として、さらなる通信環境の向上が不可欠とされています。メタバースやAR/VRなど、新たなデジタル体験の実現に向けて、通信インフラの進化は重要な役割を果たすことでしょう。
レンダリング技術の進歩
リアルタイムレンダリング技術は、現在のメタバース普及における大きな課題となっています。処理負荷の高さは、動きの不自然さや音声の途切れなどのサービス品質の低下を引き起こすか、あるいはユーザー側に高性能な機器や高速な通信環境の導入を強いることになります。これらの要因が、メタバースの一般普及を妨げる原因となっています。
レンダリング技術の更なる発展により、これらの課題が解決されれば、メタバースの利用体験は大きく改善され、より広い層への普及が期待できます。
遅延の低減
遅延問題の解決には、ネットワークインフラの強化だけでなく、3Dデータの効率的な圧縮技術など、複数の技術領域での改善が必要です。幸いにも、これらの技術は着実に進歩を続けており、ユーザー体験の質は徐々に向上しています。サービス提供者には、この課題に対する継続的な取り組みが求められています。
VRデバイスの普及
VRデバイスの普及が進んでいることで、性能向上と価格低下が並行して進んでいます。
VRデバイスそのものについても、メタバースに利用する以外に通常の映像コンテンツやゲームを楽しむなど、VRデバイスを買って「損をしない」程度には利用シーンが増えてきています。
やはりメタバースを楽しむにあたってVRデバイスはぜひ揃えておきたい機材ですので、入手がしやすくなっている現状は追い風となるでしょう。
デジタルツインの実装
デジタルツインとは、現実世界の対象物を大量のデータに基づいてデジタル空間上に精密に再現する技術です。「デジタルの双子」という名称の通り、現実の存在物の完全なデジタルコピーを作り出すことを目指しています。
この技術は人間の再現だけでなく、工業製品や設備などにも広く応用されています。例えば、航空機の機体をデジタルツインとして再現することで、実機を使用せずに故障診断や事故シミュレーションを行うことが可能となります。これにより、安全性の向上とコスト削減を同時に実現できます。
デジタルツインとメタバースは、本質的に異なる概念です。デジタルツインが実在するものの精密なデジタルコピーであるのに対し、メタバースではアバターの背後に実際の操作者が存在します。しかし、技術の発展に伴い、メタバース空間での接客にデジタルツインを活用したり、デジタルツインによるシミュレーション環境をメタバース内に構築したりするなど、両者の境界は次第に曖昧になっていくと予想されます。
なお、メタバースを含む日本のWeb3市場は世界有数の成長率と言われています。詳しくは『日本は世界有数のWeb3国家になる?Web3の今後の将来性を解説』をご覧ください。
まとめ
メタバースは普及しない・意味がないといわれることがありますが、過去に失敗したメタバースの事情と、現在の環境は異なっています。
また、IT関係の技術の進歩は現在でも速いスピードで起こっているため、メタバースがビジネス的に成功する瞬間は、想像よりも早く訪れる可能性もあります。
メタバースビジネスの展開や投資を検討している方は、関連技術の進歩や話題性などを見極めながら、トレンドを分析していきましょう。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
メタバース関連では、OASISの開発・運営の実績があるMCB Web3支援サービスを掲載しております。
その他にも、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

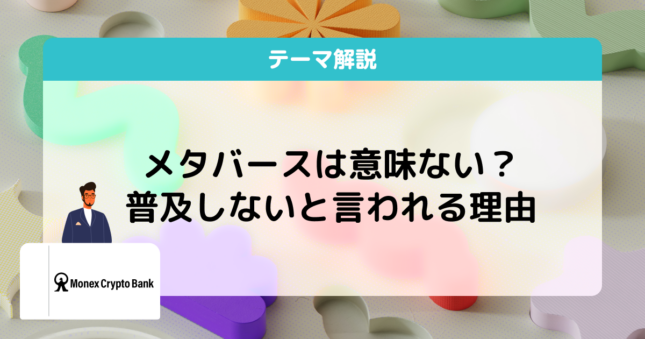

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




