人口減少に伴う国内需要の縮小をカバーするための対策として、近年はグローバル需要の取り込みや企業の海外市場への進出がますます重要視されています。
企業や個人事業主が海外の顧客や取引先、サプライヤーなどと取引をするには、「クロスボーダー取引」を行う必要があります。クロスボーダー取引とはその名の通り、国境を越えて行われる財やサービスの取引のことを指します。
クロスボーダー取引には、取引に関するルールや決済方法、手数料などの点で国内間での取引とは異なるポイントがいくつかあります。そのため、海外の企業やサプライヤーとの取引を検討している事業者は、事前にそれらについての知識を身につける必要があります。
そこでこの記事では、クロスボーダー取引の特徴と用途、各種手段、メリット・デメリットなどについて解説していきます。さらに、近年新たなクロスボーダー取引の方法として注目を集めている、ブロックチェーンを活用した暗号資産による送金・決済方法についても解説します。「海外市場の進出を検討している」という方は、ぜひご覧ください。
目次
クロスボーダー取引とは
クロスボーダー取引とは、国境を越えて行われる個人、企業、金融機関間の財やサービスの取引を指します。海外に支社や取引先、サプライヤー、請負業者などがいる企業や個人事業者にとって欠かせない取引方法で、国際取引や海外取引とも呼ばれています。
通常、クロスボーダー取引を行う際には、金銭を支払う側は通貨を別の通貨に換算して支払います。例えば、日本の企業からアメリカの企業に送金する場合、円をドルに換算してから送金するのが一般的です。
クロスボーダー取引で生じる為替リスク
クロスボーダー取引で外貨建取引を行う場合、金額を支払う側には為替の変動に応じて損失が生じるリスクがあります。
例として、1万ドルで商品を購入したケースを考えてみましょう。取引時に「1ドル=100円」の場合は100万円の費用で済みますが、決済時に「1ドル=120円」に変動した場合は120万円を支払わなくてはなりません。この差額の20万円は、為替の変動によって生じた損失です。
反対に、決済時に「1ドル=80円」に変動した場合、支払額は80万円となります。この場合は20万円の為替差益を得ることができます。
クロスボーダー取引を行う企業や個人は、このような為替変動の他にも、相手先の国の規制や銀行取引における慣行なども考慮して取引をする必要があります。
為替リスクを回避するための方法
為替の変動によって決済額に影響を及ぼす為替リスクは、自国通貨建て(日本企業なら円建て)で取引をすることで回避することができます。
しかし、もし自国通貨建てで取引を行う場合、今度は取引相手側に同様の問題が発生することになります。当然、相手方も為替リスクは避けたいと考えるのが自然なため、例えばアメリカの企業ならドル建てでの取引を希望されるケースが多くなります。なお、決済通貨に関しては、取引の相手方と交渉して決めるのが一般的です。
もしドル建てでの取引が必要な場合、為替予約をすることで為替リスクを回避することができます。為替予約とは、将来予定している海外の取引相手との商品売買などに関して、事前に通貨・金額・為替レートを取り決めて行う取引のことです。為替予約の利用者は為替相場の影響を受けずに取引を行うことができるため、もし決済時に円安に推移しても当初想定していた金額で決済することができます。
クロスボーダー取引の用途
クロスボーダー取引の用途には、主に以下のようなものがあります。
- 商品・サービスの購入
- 外国勤務の従業員への給与支払い
- 海外資産の購入
- 海外企業への投資
- 海外の慈善団体への寄付
それぞれどのような内容なのか、順番に解説していきます。
商品・サービスの購入
海外の企業が提供する商品やサービスを購入する際には、クロスボーダー取引が行われます。例えば、「1ドル=150円」の時に海外の企業が販売している60ドルの商品を購入する場合、日本円に換算して9,000円の費用が必要になります。なお、支払方法はいくつかありますが、個人が海外の企業が提供する商品を購入する場合はクレジットカードによる取引が行われるのが一般的です。
また、国内企業が低コストで商品や部品、原材料などを仕入れるために、海外のサプライヤーと取引する際にもクロスボーダー取引が行われます。
外国勤務の従業員への給与支払い
新型コロナの影響によりテレワークが普及したことで、国境を越えて働くいわゆる「越境リモートワーク」をする人が増加しています。そして、企業が海外在住の従業員や請負業者に対して給与を支払う際には、クロスボーダー取引が行われます。また、海外在住の外国籍の人材をフルリモートで雇用する際にも、クロスボーダー取引で報酬を支払う必要があります。
海外資産の購入
海外進出を目指す企業が、海外の企業や工場、鉱山などの資産を購入する際にもクロスボーダー取引が利用されます。例えば、日本の企業がアメリカの事業者を買収する際には、クロスボーダー取引が行われます。
海外企業への投資
国内の企業が海外の企業、プロジェクト、不動産などに投資する際にもクロスボーダー取引が行われます。例えば、アメリカのベンチャーキャピタルが日本のスタートアップ企業に投資する際には、クロスボーダー取引が利用されます。
外国の慈善団体への寄付
企業がSDGs、CSR活動の一環として海外の慈善団体に寄付をする際にも、クロスボーダー取引が行われる場合があります。
クロスボーダー取引の手段
続いて、クロスボーダー取引を行う際の手段について解説していきます。ここでは、代表的な手段である以下の5つについて解説していきます。
- 電信送金
- クレジットカード取引
- 外国為替
- オンライン決済サービス
- 暗号資産
1.電信送金
クロスボーダー取引の代表的な手段としては、電信送金(Wire Transfer)が挙げられます。電信送金とは、銀行同士がやり取りをして資金を電子送金する方法です。私たちが銀行を利用して海外送金する場合、この電信送金が行われます。
ただし、銀行同士がやり取りをすると言っても、世界の銀行同士は直接的な繋がりがないケースが大半です。そのため、送金元の銀行は「SWIFT(国際銀行間通信協会)」という世界中の金融機関をつなぐ送金インフラを利用し、以下のように「コルレス銀行」と呼ばれる銀行を中継して電信送金を行います。
送金銀行→コルレス銀行(中継銀行)→コルレス銀行(中継銀行)→受取銀行(相手)
なお、電信送金には手数料が高額になりやすいという問題があります。これには、送金手数料のほかに、コルレス銀行に支払う中継銀行手数料や為替手数料など、支払う手数料の種類が多いことに原因があります。
送金総コスト = 送金手数料 + 中継銀行手数料 + 為替手数料 + (場合により)着金手数料
2.クレジットカード取引
クレジットカードは、世界中の多くの企業や店舗に採用されている決済手段です。クレジットカードの利用者は、インターネットなどを通じて海外の店舗が販売している商品を購入することができます。
なお、クレジットカードの通貨換算は買い物をした時ではなく、VISAやMastercardなどの決済センターに売上データが到着した時点で行われます(※)。
(※)参考:三井住友カード「外貨で決済した場合の換算レートについて」
3.外国為替
外国為替とは、通貨が異なる国の間で商品の輸出入、外国証券や海外不動産への投資などの取引が生じた際に、現金を介さずに為替手形や送金小切手などを使って決済する方法です。
4.オンライン決済サービス
オンライン決済サービスとは、インターネットを介して行われる商品やサービスの支払いや、代金の受け取りなどを代行するサービスです。オンライン決済サービスの中には、決済だけでなく海外への送金や海外からの資金の受け取りに対応しているものもあります。これらのサービスは、通常PCやスマートフォンアプリを使って操作します。
なお、世界で利用されているオンライン決済サービスには以下のようなものがあります。
- PayPal
- Amazon Pay
- Alipay
- Stripe
- Square
5.暗号資産
近年は、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの暗号資産も、ボーダーレスな決済・送金方法として注目を集めています。
暗号資産は送金人と受取人の双方がウォレットを持っていれば、銀行などの金融機関を介さずに送金することが可能です。なお、暗号資産を送金する際には、マイナーと呼ばれる取引を承認する作業を行う人に手数料を支払う必要があります。
決済手段としては、暗号資産はクレジットカードなどと比べるとまだそれほど普及していません。それでも、ビットコインなどの暗号資産を決済手段として受け入れる企業や店舗は徐々に増えてきています。現在は一時停止中ですが、2021年には米電気自動車大手のテスラがビットコイン決済を導入したことで話題を呼びました(※)。
(※)参考:日本経済新聞「テスラのEV、ビットコインで購入可能に まず米国で」
クロスボーダー取引のメリット
クロスボーダー取引には、主に次のようなメリットがあります。
- 海外市場の開拓
- 売上拡大
- コスト削減
- 従業員満足度(ES)の向上
どのような内容なのか、順番に見ていきましょう。
海外市場の開拓
クロスボーダー取引を導入することで、企業は海外市場に進出することができるようになります。それにより、新たな顧客や取引先、サプライヤーなどを確保することができます。
また、海外展開することで企業名も世界中に広められるため、グローバルブランドの構築を実現することも可能になります。
売上拡大
海外販路を開拓することで、国内だけの営業に比べて売上を拡大させることができます。また、国内とは異なる技術や資源をもつ現地の企業と協働することで、新商品の開発や新規プロジェクトの発足など、新たなビジネスチャンスを創出することも可能になります。
コスト削減
クロスボーダー取引を導入することで、企業は人件費が安い海外の人材を雇用したり、原価が安い海外の工場から部品を仕入れたりできるようになります。これにより、国内市場だけで調達するよりも、必要な人材や物を安価に揃えることができます。
従業員満足度(ES)の向上
企業は従業員に対して多様で柔軟な働き方を提供することで、従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)を上昇させることができます。一般的に、従業員満足度が高まると従業員のモチベーションや定着率、生産性などが向上すると言われています。
その点、クロスボーダー取引を導入し、従業員の海外でのリモートワークを受け入れることは、従業員満足度の向上につながる行為と言えるでしょう。
クロスボーダー取引のデメリット
一方で、クロスボーダー取引には次のようなデメリットもあります。
- 法規制の問題
- 為替リスク
- 送金に時間がかかる場合がある
- 各種手数料
- 業務の煩雑化
法規制の問題
クロスボーダー取引を行う際には、相手先の国の法規制を遵守する必要があります。
各国にはマネーロンダリングやテロ資金供与を防止する法律など、金融取引に関する独自の規制が存在します。そのため、海外の事業者と取引をする際には、国内の規制だけでなく相手先の国の法律も調べて取引内容に問題がないかを確認する必要があります。
為替リスク
クロスボーダー取引は、為替の変動によって想定していた額とは異なる金額の支払いを求められる場合があります。このような為替リスクは、企業のキャッシュフローに多大な影響を与えます。そのため、企業の財務部門は為替リスクによる影響を最小限に抑えるようにキャッシュフローを管理し、資金繰りの安定化を図る必要があります。
送金に時間がかかる場合がある
クロスボーダー取引は、決済手段によっては国内送金と比べて送金に時間がかかる場合があります。例えば電信送金の場合、中継銀行の処理にどの程度時間がかかるかにもよりますが、相手先に着金するまでに大体1週間程度を要します(※)。
(※)参考:株式会社SMBC信託銀行「海外送金の資金はどのくらいで届きますか?」
各種手数料
クロスボーダー取引の手数料は、決済手段や相手先がどこの国なのかによって異なります。例えば、銀行を介して送金する電信送金の場合、送金手数料のほかに為替手数料や中継銀行手数料などがかかるため、国内取引と比べて手数料が高額になります。
業務の煩雑化
前述したように、クロスボーダー取引を行う企業は、取引相手先の国の法規制を遵守したり、為替リスクを考慮してキャッシュフローを管理したりする必要があります。そのため、国内取引と比べて業務が煩雑になりやすいという問題があります。
クロスボーダー取引にブロックチェーンを利用するケースが増えている理由
近年はブロックチェーンの台頭により、ビットコインなどの暗号資産を用いた送金・決済も存在感を増してきています。
ブロックチェーンとは、暗号技術によってネット上の取引履歴を記録・管理する仕組みのことです。「ブロック」と呼ばれる取引データを鎖のように次々とつないでいく構造を持つことから、ブロックチェーンという呼び名がついています。
特定のサーバーが情報を一元管理する従来の中央集権的なシステムとは異なり、ブロックチェーンではネットワークに参加する個々のノードが分散して取引履歴のデータを管理します。さらに、ブロックチェーン上での取引では、分散型台帳技術(DLT)や公開鍵暗号技術といった高度な技術が使われおり、特定の管理者が不在でも安定・安全に取引を行うことができるシステムが構築されています。
ブロックチェーンを使用する暗号資産取引は、前述したクロスボーダー取引の「送金までに時間がかかる」「手数料が高額になりやすい」といった問題をクリアする決済方法として、世界中で注目を集めています。従来の銀行送金よりも手数料が安く、ボーダーレスに素早く送金ができる利点から、暗号資産とブロックチェーンを活用した国際送金サービスは今後さらに増加していくことが予想されます。
クロスボーダー取引にブロックチェーンを利用するメリット
ブロックチェーンには、人の手を介さずに自動で契約内容を実行できる「スマートコントラクト」という機能があります。この機能があるため、暗号資産を使用した送金・決済では、銀行やオンライン決済サービスのような第三者による仲介が必要ありません。
そのため、ブロックチェーンは取引を行うのに必要な人(機関)やプロセスを減らすことができ、その分コストの削減や取引時間の短縮を実現することができます。この「コスト削減」と「迅速な取引」が、ブロックチェーンを使用した暗号資産取引の主な利点を言えるでしょう。
以下の表は、電信送金などの従来のクロスボーダー取引と、ブロックチェーンを利用したクロスボーダー取引の主な違いを比較したものです。
| 従来のクロスボーダー取引 | ブロックチェーンを利用したクロスボーダー取引 | |
| 仲介者 | 銀行、クレジットカード会社、オンライン決済サービスなど | スマートコントラクト機能があるため、仲介者は不要 |
| 取引時間 | 決済手段による。仲介者の数が増えるほど取引にかかる時間が増加する | 相手と直接取引ができるため、迅速な取引が可能 |
| 手数料 | 決済手段による。仲介者の数が増えるほど手数料も高額になる | 仲介者がいないので低コストな取引が可能 |
表からもわかるように、従来の取引方法とブロックチェーンを利用した取引方法の最大の違いは、「仲介者の有無」です。ブロックチェーンを利用した取引方法では第三者を介さずに相手と直接やり取りできるため、スピーディーで低コストな取引ができるのです。
まとめ
ここまで、クロスボーダー取引の概要と用途、手段、メリット・デメリット、ブロックチェーンを活用した取引方法などについて解説してきました。
国境を越えて財やサービスの取引を行うクロスボーダー取引には、主に次のようなメリットがあります。
- 海外市場の開拓
- 売上拡大
- コスト削減
- 従業員満足度(ES)の向上
しかしその反面、クロスボーダー取引には「取引に時間がかかる場合がある」「手数料が高くなりやすい」といったデメリットもあります。そのような問題を解消する方法として、近年はブロックチェーンと暗号資産を利用した取引方法が注目を集めています。電信送金などの従来の取引手段と比べて手数料が安く、ボーダーレスかつ迅速に取引できるブロックチェーン取引は、今後さらに普及していくことが予想されます。
また、高度な技術が使用され高い利便性を誇るブロックチェーンは、業務効率化・コスト削減のためのツールとしてもさまざまな業界から注目を集めています。『ブロックチェーンの活用事例を紹介!ビジネスで活用するメリットは?』では、ビジネス活用に役立つブロックチェーンの活用事例を解説しているので、ぜひご覧ください。
最後に、MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
「Web3事業を新しく立ち上げてみたい」「国内の暗号資産規制に準拠したWeb3の活用方法から事業化までの支援を受けたい」など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

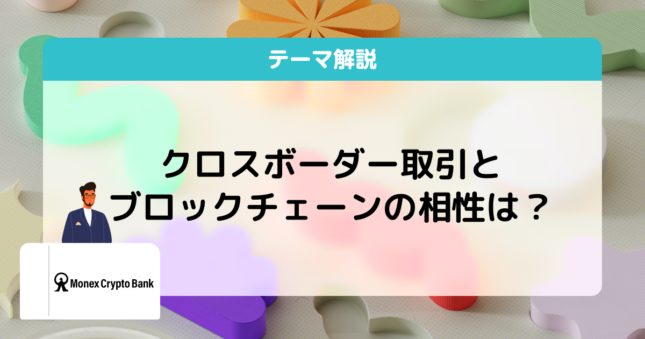

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




