近年注目を集めるブロックチェーンゲームは、革新的な技術を用いた新たなエンターテインメントとして話題を呼んでいます。しかし一方で、「流行らない」「オワコン」といった否定的な意見も少なくありません。果たして、ブロックチェーンゲームに未来はないのでしょうか?それとも、新たな可能性を秘めているのでしょうか?
この記事では、ブロックチェーンゲームの現状と課題、さらにそれを取り巻く市場や技術の背景について深掘りします。また、なぜ「流行らない」と言われるのか、その理由を多角的に分析し、ゲーム業界全体との比較も行います。さらに、ブロックチェーンゲームが「オワコン化」しないための具体的な改善点や、今後期待される展望についても解説します。
目次
ブロックチェーンゲームは本当に流行らないのか
ブロックチェーンゲームは新しい技術を活用したエンターテインメントとして注目されています。しかし、その持続的な人気獲得には課題が多いとされています。一方で、単発的な流行を生み出した成功事例も存在し、その可能性を完全に否定することはできません。
ここでは、ブロックチェーンゲームがどのような流行を生み出しているのか、またその持続性に影響を与える要因について詳しく掘り下げます。
単発的な流行は発生している
ブロックチェーンゲームの中には、一時的に爆発的な人気を獲得した例があります。その代表格として挙げられるのがGameFiの「STEPN」です。
STEPNは、プレイヤーがNFT化されたスニーカーを購入し、日々の歩数に応じて暗号資産を稼ぐ「Move-to-Earn」という新しい収益モデルを提供しました。この仕組みは、健康志向の高まりやライフスタイルの変化に見事にマッチし、多くのユーザーの関心を引きつけました。
STEPNはとくに、コロナ禍における外出制限の時期に多くの支持を集め、短期間で大きな成功を収めました。
しかし、この成功は長く続かず、NFT価格やゲーム内トークンの価値が急速に下落し、利益を重視していた多くのユーザーがゲームから離脱しました。この事例は、ブロックチェーンゲームが短期的な注目を集める力を持つ一方で、その持続性に課題があることを浮き彫りにしています。
継続的なブーム形成の課題
ブロックチェーンゲームが長期的な人気を維持するのが難しい一因として、ゲームそのものの魅力が乏しい点や、ブロックチェーンゲーム特有の経済構造が挙げられます。
従来の人気ゲームは、ゲームプレイやストーリー性、長期間にわたりユーザーを楽しませるコンテンツの提供によって成り立っています。しかし、ブロックチェーンゲームの多くは「稼ぐこと」を主な目的としており、ゲーム性やエンターテインメント性が軽視される傾向があります。
さらに、ブロックチェーンゲーム特有の経済構造も課題となっています。多くのゲームでは、ユーザーの利益源は新規参入者によって支えられているため、新規参入者を入れ続けなければならず、新規参入者も稼げなければ口コミが悪くなりユーザーが増えないといった課題があります。
法的規制・税制の影響
ブロックチェーンゲームの発展を阻むもうひとつの大きな要因として、法的規制や税制の問題があります。とくに日本では、暗号資産やNFTに関連する法律が複雑で、これが新規参入者にとって大きな障害となっています。たとえば、ゲーム内で得た収益が所得税の対象となる場合、その計算や申告の負担が大きく、これがユーザーを遠ざける要因となっています。
ブロックチェーンゲーム流行らない・オワコンとされる理由
ブロックチェーンゲームは、「稼げるゲーム」として広く認知され、その特性が多くのプレイヤーを惹きつけてきました。しかし、その「稼げる」という点が裏目に出るケースも少なくありません。この章では、稼ぐことへの過剰な期待、市場の変化、そしてゲームデザインの課題について順を追って解説します。
理由1.稼ぐことへの過剰な期待
ブロックチェーンゲームの収益モデルは、暗号資産・NFT市場が盛り上がっていた時期に注目を集めました。この背景には、暗号資産への投資熱があり、ゲームを通じて「稼ぐ」ことがユーザーに大きな期待を抱かせたのです。しかし、この期待が過剰になると、収益性が低下した際にゲーム全体の評価が急落するリスクを伴います。
たとえば、ユーザーがゲーム内トークンを獲得しても、市場でその価値が急落すれば、ゲームに費やした時間や努力が無駄だと感じることがあります。このような状況は、収益を重視するユーザーが一斉にゲームを離れるきっかけとなります。
また、ブロックチェーンゲームのユーザー層は、収益性が高い間は急増しますが、逆に収益性が低下した途端、多くのユーザーが他の収益機会を求めて去っていきます。この「稼ぐこと」を基準にしたプレイヤー動向が、ブロックチェーンゲームを「オワコン」と見なされる主要因のひとつです。
理由2.市場変化と競争の激化
市場の変化も、ブロックチェーンゲームの安定性を脅かす大きな要因です。暗号資産市場全体の価格変動や規制の影響を受けやすく、ゲーム内の収益性が安定しないという課題があります。この不安定さが、ユーザーの期待と現実の間に大きなギャップを生む原因となっています。
たとえば、暗号資産の価格が上昇している時期には、ゲーム内トークンの価値も上昇し、多くのプレイヤーが利益を得ることができます。しかし、市場が下落に転じると、トークンの価値が急激に下がり、プレイヤーが損失を被るケースが頻発します。このような市場変動に伴う収益性の低下は、ゲームの人気を短期間で失わせる要因となるのです。
さらに、ブロックチェーンゲーム市場では新規ゲームの参入が相次ぎ、競争が激化しています。新しいゲームがより高い収益性や独自のアイデアを提供することで、既存のゲームからユーザーが流出する現象が見られます。この競争環境が、既存のブロックチェーンゲームの持続的な成長を阻んでいるのです。
理由3.ユーザーの期待値とゲームデザインの課題
プレイヤーがブロックチェーンゲームに求めるものは、「稼ぐこと」だけではありません。エンターテインメント性やゲームそのものの楽しさも重要な要素です。しかし、収益性を主軸に設計されたブロックチェーンゲームでは、これらの要素が軽視される傾向があります。その結果、収益性が低下した際にプレイヤーを引き留める魅力が不足しています。
さらに、多くのブロックチェーンゲームでは、収益モデルに新規参入者が不利な仕組みが内包されています。たとえば、初期投資が必要であったり、利益が初期ユーザーに偏って分配されたりする場合、新規ユーザーは不公平感を抱き、参加を躊躇します。このような構造では、新規ユーザーを引きつけることが難しく、ユーザー基盤の拡大が滞る結果を招きます。
これらの課題を克服するためには、ゲームそのものの楽しさや魅力を高めることが不可欠です。また、「稼ぐこと」を目的としないプレイヤー層を取り込むことで、収益性が低下してもユーザーを維持する仕組みが求められます。これこそが、ブロックチェーンゲームが「オワコン」と見なされる状況を打破するカギとなります。
理由4.参入障壁が高く一般人が参入せず
ブロックチェーンゲームが普及しにくい大きな要因のひとつが、参入障壁の高さです。とくに、ウォレットを作成し、暗号資産を準備する手間が、初心者にとって大きなハードルとなっています。
ブロックチェーンゲームをプレイするには、多くの場合、専用の暗号資産ウォレットが必要です。ウォレットの作成にはアカウント登録や秘密鍵の管理が必要で、これらの手続きは初心者にとって非常に難解です。また、取引所での本人確認や資産送金の手間も加わり、参入へのハードルをさらに高めています。
また、暗号資産に関連する法的規制や価格変動のリスクも初心者を遠ざける要因です。これらの課題により、ブロックチェーンゲームは特定の技術に詳しい層に限定され、一般層への普及が難しい状況です。
理由5.ゲームにブロックチェーンを組み込む必要性が乏しい
ブロックチェーン技術が必ずしもゲームデザインに不可欠とは言えない場合もあります。開発者が技術トレンドに従うためにブロックチェーンを導入しているケースでは、ゲーム体験の向上には寄与しない場合があります。
ゲーム内アイテムや通貨をNFT化しても、それがプレイヤーにとって本質的な価値を持たない場合、ブロックチェーン技術の意義が薄れることがあります。くわえて、技術導入のコストや開発時間が増加する一方で、プレイヤーが得られる体験がそれに見合わない場合、技術的な新規性が逆にゲームの負担となることもあります。
こうした課題を解決するには、ブロックチェーン技術を導入する目的を明確にし、プレイヤーにとって真の価値を提供するデザインが必要です。技術がゲーム体験を向上させる形で統合されていることが、ユーザーにとっての納得感を高めるカギとなります。
ゲーム業界ではブロックチェーン・NFTへの対応が二分
ゲーム業界では、ブロックチェーンやNFT技術の導入について、各企業やプラットフォームが異なる姿勢を示しており、対応が二分化しています。一部のプラットフォームは技術のリスクを重視して規制を強化する一方で、積極的に新たな可能性を追求する企業もあります。
STEAM:ブロックチェーンゲームやNFTは排除の方向
世界最大級のゲーム配信プラットフォームであるSTEAMは、ブロックチェーン技術やNFTに対して否定的な立場を取っています。STEAMのコンテンツ配信ガイドラインでは、「暗号通貨またはNFTの発行や交換を許可するブロックチェーン技術に基づいて構築されたアプリケーションは、Steamで公開すべきではないもの」と明記されています。
出典:https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/onboarding
このポリシーは、暗号資産やNFTが絡む詐欺的なプロジェクトや不透明な取引を防ぐためとされています。近年、NFT関連のプロジェクトには一部で不正行為が見られ、消費者の信頼を損なう事例が報告されてきました。
そのため、STEAMは自社プラットフォームの健全性を維持するために、これらの技術を活用したゲームの配信を制限しています。
この対応により、STEAMはユーザーの保護を最優先にした運営を行っていますが、暗号資産やNFTの技術を活用したい開発者にとっては大きな障害となっています。STEAMの規制は、消費者保護と技術革新のバランスをどのように取るべきかという課題を示唆しています。
スクウェアエニックス:ブロックチェーンゲームを発表
一方で、スクウェアエニックスはブロックチェーン技術の活用に積極的です。同社は「Symbiogenesis」というタイトルでNFTを活用したブロックチェーンゲームを発表し、新しいゲーム体験の提供を目指しています。Symbiogenesisは、NFTキャラクターを収集し、それをゲームプレイに活用しながら進行するストーリー主導型のゲームです。
公式サイトによれば、このゲームではNFTが単なる収益手段ではなく、ゲーム体験の中核要素として活用されています。また、技術的な詳細は公式技術文書で公開されており、透明性の高い運営が行われています。
スクウェアエニックスは、公式X(旧Twitter)アカウントを通じてSymbiogenesisの進捗や最新情報を発信しています。この取り組みは、プレイヤーにとって新しい価値を生むことを目的としており、ゲーム体験の一部としてNFTを自然に組み込むことで、ブロックチェーン技術を単なる付加価値としてではなく、ゲームの本質的な要素として利用しようとしています。
STEAMとスクウェアエニックスという対照的な例を見ても、ブロックチェーンやNFTに対するゲーム業界の対応が二分していることが分かります。STEAMは消費者保護を重視して技術の利用を制限する一方で、スクウェアエニックスは新たなエンターテインメントの形を模索しています。この二極化した対応が今後のゲーム市場に与える影響は大きく、業界全体としての方向性が注目されています。
ブロックチェーンゲームをオワコン化させない根本的改善点
ブロックチェーンゲームが直面する課題を乗り越え、持続可能な市場を構築するためには、根本的な改善が必要です。従来の「稼ぐ」ことを目的としたモデルから脱却し、プレイヤーがゲームそのものを楽しむ仕組みを作ることが重要です。
ここでは、ブロックチェーンゲームをオワコン化させないための具体的な改善点を解説します。
「稼ぐ」ことを念頭に置かないゲーム設計
多くのブロックチェーンゲームが「Play-to-Earn(稼ぐために遊ぶ)」というコンセプトを中心に設計されていますが、このモデルはプレイヤーが収益性を求めすぎるあまり、ゲーム自体の楽しさを犠牲にしているケースが目立ちます。プレイヤーが「稼げなくなった」と感じた瞬間に離脱する傾向が強く、この構造がゲームの寿命を短くしています。
この課題を克服するためには、「稼ぐ」ことを主目的としない設計が求められます。たとえば、ストーリー性の強化やゲームプレイそのものの充実を図り、プレイヤーが純粋に遊びたくなるような仕組みを作る必要があります。ゲームとしての価値が確立されれば、「稼ぐ」という要素が付加価値として自然に組み込まれる形になり、より持続可能なゲームモデルが実現します。
獲得できるアイテム・NFTにコレクション性を持たせる
NFTの活用はブロックチェーンゲームの特徴のひとつですが、その使い方によってゲームの成功が大きく左右されます。単なる収益手段としてのNFTではなく、コレクション性を持たせることで、プレイヤーに新たな魅力を提供することが可能です。
たとえば、トレーディングカードゲーム(TCG)を例に挙げると、対戦での勝利よりも、特定のカードを集める楽しさを重視するプレイヤーが存在します。ゲームアイテムにコレクション性を持たせることで、投資目的ではなく純粋にアイテムそのものに価値を感じるプレイヤー層を形成できます。これにより、
NFTが投機的な目的から解放され、より長期的にゲームを楽しむプレイヤーを引きつけることが期待されます。
また、希少性やデザイン性を高めることで、NFTそのものが文化的な価値を持つアイテムとして認識されるようになることもあるでしょう。このようなアイテムは所有するだけで満足感を得られるため、プレイヤーの収集欲を刺激し、ゲームの継続性を向上させる効果が望めます。
新規ユーザーも稼げる環境を作る
ブロックチェーンゲームが抱える課題のひとつは、初期ユーザーに利益が集中し、新規ユーザーが参入する意義を見いだしにくい点です。この構造を改善することで、新規ユーザーが継続的に増加し、ゲームの活性化につながります。
具体的には、新規ユーザーがゲーム内経済に参加しやすい仕組みを設計することが重要です。たとえば、初期投資を必要としない無料プレイモデルや、新規参入者向けの報酬システムを導入することが効果的です。また、新規ユーザーが成長する過程で獲得するリソースが、既存ユーザーとも競争せずに価値を持つような経済設計を考える必要があります。
さらに、新規ユーザー向けのチュートリアルやサポートを充実させることで、ブロックチェーンやNFTに不慣れな人々でも安心してゲームを楽しめる環境を整えることが求められます。このような仕組みを取り入れることで、ゲームの普及と持続可能性が大幅に向上します。
ブロックチェーンゲームのエコシステムはまだ発展途上であるため、既存のソーシャルゲームのようにエコシステムが確立されることで、発展する可能性が見込まれるでしょう。
ブロックチェーンを組み込んだからこそ「面白い」ゲームを作る
最後に、ブロックチェーン技術を単なる「目新しさ」として利用するのではなく、その特性を活かした「面白い」ゲームを作ることが重要です。現在、多くのブロックチェーンゲームは技術の導入が目的化しており、ゲームとしての完成度が二の次になっています。この問題を解決するには、ブロックチェーンの利点をゲーム体験に直結させる工夫が必要です。
たとえば、ブロックチェーンを活用してプレイヤー間の取引をよりスムーズにしたり、ゲーム内のアイテムが完全に所有権を持つ形で管理したりすることで、新しい種類のエンターテインメントが生まれます。また、スマートコントラクトを使ったプレイヤー間の自動的なイベント生成や、ゲーム内での透明性の高い報酬システムも、プレイヤーに独自の価値を提供する可能性を秘めています。
こうした工夫により、ブロックチェーン技術が単なる収益手段ではなく、ゲームの面白さそのものを引き立てる役割を果たすようになります。プレイヤーが「ブロックチェーンを使っているからこそ楽しい」と感じるゲームが登場すれば、ブロックチェーンゲームの評価は大きく変わるかもしれません。
ブロックチェーンゲームを「オワコン」とさせないためには、これらの改善点を取り入れたゲームデザインが必要です。単に技術を導入するだけでなく、プレイヤーにとって価値のある体験を提供することが、長期的な成功につながるカギとなります。
ブロックチェーンゲームの今後の展望
ブロックチェーン技術の進化に伴い、ゲーム業界での応用が進んでいます。
メタバース系ゲーム内での経済圏を確立する
メタバース系ゲームでは、仮想空間内での経済活動が重要な役割を果たします。ブロックチェーン技術を活用することで、ゲーム内アイテムや通貨をNFT化し、プレイヤー間の取引を安全かつ透明にすることが可能になります。
ブロックチェーンを活用した経済圏の構築は、従来のゲームでは得られなかった新しい体験をプレイヤーに提供します。これにより、ゲームを「遊ぶ」だけでなく、「作る」「取引する」活動が可能になり、ユーザーエクスペリエンスが多面的に向上することが期待されます。
ブロックチェーン・NFTの活用は排出確率の管理に留め課金を刺激する
ガチャシステムの排出確率に関する透明性は、現在の課金型ゲームの主要な課題のひとつです。プレイヤーの間では不透明なガチャ排出が問題視されており、公称レートとの乖離が指摘されるケースもしばしば存在します。
ブロックチェーン技術を利用すれば、ガチャの排出確率を明確に公開することになります。これにより、プレイヤーにとって信頼性が向上し、課金に対する心理的ハードルが低下する効果が期待されます。また、強力なアイテムの排出数も把握でき、プレイヤーが心理的な優位性を獲得するための課金に繋がる可能性があります。
従来のRMT程度の市場規模に落ち着かせる
ブロックチェーン技術を利用したゲームでは、リアルマネートレード(RMT)の詐欺リスクが軽減され、ユーザー間取引の信頼性が向上します。従来のRMTは、アイテムの売買や取引において詐欺的行為が問題となっていましたが、ブロックチェーン技術を導入することで透明性が確保され、安全な取引環境を実現できます。
市場規模としては、RMTと同程度に収めることで、ギャンブル性を排除し、健全な取引環境を構築できる可能性があります。また、スマートコントラクトの活用によりアイテムの「レンタル」も安全に行うことができるため、従来のRMT市場よりもユニークな取引ができ、取引が活発化する可能性もあります。
これにより、ゲーム内経済がより多くのユーザーに受け入れられる形を作れるかもしれません。
既存のゲームやIPをブロックチェーンゲーム化する
既存の人気IPをブロックチェーン技術でリメイクすることは、古くからのファン層を取り込み、新たな価値を提供する可能性を秘めています。
とくにレトロゲームでは、ゲーム自体の容量が小さく技術的な実装が比較的容易であるため、DOOMなどは実験的な環境で再現する例も多くあります。そのため、レトロゲームのブロックチェーン化によるリメイクは有望な選択肢と言えるでしょう。
実例:1981年発売 シリーズ「Wizardry(ウィザードリー)」Eternal Crypt – Wizardry BC

参照:https://wiz-eternalcrypt.com/
1981年に発売された「Wizardry」シリーズは、クラシックなRPGとして世界中で人気を集めました。このシリーズをベースにしたリメイク作品「Eternal Crypt – Wizardry BC」は、ブロックチェーン技術を導入し、ゲーム内アイテムをNFTとして取引可能にしています。
NFT化により、アイテムがゲーム終了後もプレイヤーの資産として残る仕組みを採用しています。また、サーバー不要で自律的に稼働する設計が特徴であり、ブロックチェーンの特性を活かした新しい形のゲームとして注目されています。
ブロックチェーンゲームの未来には多くの可能性が広がっています。Eternal Crypt – Wizardry BCのような事例は、過去のIPを活用したリメイクが新たな成功の形となる可能性を示しています。このような展望を実現するためには、技術の透明性を保ちつつ、プレイヤーに価値ある体験を提供することが重要です。
まとめ
ブロックチェーンゲームが「オワコン」といわれる理由を理解することで、持続可能なゲーム設計の可能性が広がります。「稼げる」だけではなく、ゲームとしての「面白さ」を重視することが、長期的な成功を実現するカギです。ブロックチェーン技術は、アイテムの所有権や取引の透明性を高め、ゲーム体験を新たな次元へ引き上げる可能性を秘めています。
重要なのは、ブロックチェーンを単なる付加価値として利用するのではなく、ゲーム全体の楽しさを引き立てる要素として取り入れることです。プレイヤーが「遊びたい」と感じるゲームを提供することで、ブロックチェーンゲームが抱える課題を克服し、新しい市場を築く基盤を作り出せます。
また、専門知識を持つコンサルティングサービスの活用は、ブロックチェーンゲームの可能性を最大化するために効果的です。こちらの『【徹底比較】ブロックチェーン開発で注目の企業13選!各社の実績と特徴を解説』 では、ブロックチェーン開発やWeb3事業の推進におすすめの開発企業を厳選し、ゲームに特化したブロックチェーンの企画・開発サービスを提供している企業も紹介しています。あなたのプロジェクトに最も適した企業を簡単に見つけることができると思います。
このような支援を取り入れることで、技術とゲーム性をバランスよく統合し、プレイヤーにとって魅力的な体験を生み出すことが可能です。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- 「ブロックチェーンゲームの開発を専門家に相談したい」
- 「ブロックチェーンゲームに活用することのできるサービスやソリューションを比較検討したい」
など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

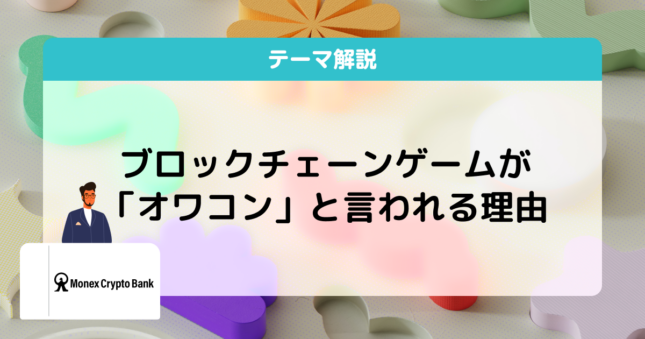

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




