「フィンテックとブロックチェーンの関係性は?」「ブロックチェーンが使われているフィンテック事例を知りたい」
本記事では、これらフィンテックやブロックチェーンに関心がある方に向けて、フィンテックとブロックチェーンの概念とサービス、それぞれの関連性についての基礎知識を詳しく解説します。
目次
フィンテックとは
フィンテック(FinTech)とは、Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語です。広義の金融と技術を掛け合わせたサービスという意味では、初期の送金システムが確立された1800年代がフィンテックのおこりであるともいわれています。
しかし一般的にフィンテックは、金融とIT技術を組み合わせた新しい金融サービスのことを指し、2000年代から徐々にサービスの幅が広がってきました。本記事でも、フィンテックは2000年代以降のIT技術を組み合わせたサービス全般のこととして説明します。
フィンテックの主要分野
では、フィンテックとは具体的にどのようなサービスをさすのでしょうか。それを理解するために、代表的なフィンテックの例を見ていきましょう。
1.キャッシュレス決済
フィンテックの代表例のひとつ目はキャッシュレス決済です。その名の通り、現金(キャッシュ)を使わずに支払いをおこなえる決済の総称です。キャッシュレス決済には、大きく分けて前払い(プリペイド)、即時払い(デビット)、後払い(ポストペイ)という3種類の支払い方法があります。
決済方法は、クレジットカード決済、QRコード決済、電子マネー決済、デビットカード決済などに細分化されます。それぞれ仕組みは異なるものの、ネットワーク通信やリアルタイムの認証・承認システムなど、IT技術が使われていることは共通しています。複数あるフィンテックのサービスの中でも、普段の生活でもっとも身近に感じるものかもしれません。
2.暗号資産・ブロックチェーン
暗号資産は、ブロックチェーンという技術を基盤としたデジタル通貨です。オンライン空間のブロックチェーン上で使うことができ、ブロックチェーンに取引履歴が記録されます。暗号資産はIT技術を生かして作られたものなので、存在自体がフィンテックの一例にあたります。
さらに、ブロックチェーン上でデジタルアートや会員権の売買をおこなう場合や、国際送金をおこなう場合などの経済活動に暗号資産やトークンが使われます。このように、暗号資産の存在だけでなく、資産運用や国際送金を効率化する用途で暗号資産は活用され、フィンテックサービスが広がりを見せています。
3.クラウドファンディング・ソーシャルレンディング
クラウドファンディングとは、群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語で、インターネット上の仕組みを利用して不特定多数から資金調達することをさします。
支援者は主に個人になり、実現したいアイディアや解決したい問題などのテーマでプロジェクトが作られ、それに賛同した人が自由に支援することができます。クラウドファンディングは、商品や権利などのリターンが設定されている購入型と、リターンがない寄附型に分けられます。
ソーシャルレンディングは、金融庁によると、「インターネットを用いてファンドの募集を行い、投資者からの出資をファンド業者を通じて企業等に貸付ける仕組み」と定義されています。「金融型」や「融資型」という分類でクラウドファンディングの一種として説明されることもあります。
ソーシャルレンディングは資金調達の新しい方法ですが、現状では、残念ながら詐欺まがいの集客をおこなっている場合も一部で確認されており、金融庁も注意を促しています。
いずれも、インターネットが普及したことによって広まった金銭的な支援の方法であり、フィンテックの一種といえます。
参照:https://www.fsa.go.jp/ordinary/social-lending/index.html
4.PFM(個人財務管理)
PFMは、Personal Financial Managementの略です。厳密な定義はなく、個人の資産管理を助けるソフトウェアなどを指します。代表的なものとして、銀行口座やクレジットカードの情報を連携して、個人の資産を一元管理できる「家計簿アプリ」が挙げられます。
5.ロボアドバイザー
ロボアドバイザーは、AIなどが資産運用プランを提案してくれるサービスを指します。ロボアドバイザーには、最適な投資配分などについての提案だけをおこない、購入や投資先の変更自体は利用者みずからおこなう「アドバイス型」と、運用も含めてすべてサービス内容に含まれる「投資一任型」があります。
いずれの型も、ライフプランや、投資に対する考え方の質問に回答することで、利用者によって最善と考えられる投資プランを導き出します。資産運用への興味関心が高まっている流れにも後押しされ、さまざまな金融機関がロボアドバイザーのサービスを開始しています。
6.モバイルPOS
モバイルPOSとは、スマートフォンやタブレットなどの端末に専用アプリを入れることで、会計や在庫管理などができるサービスを指します。そもそも、POS(Point Of Sales)とは、商品が販売されたときのさまざまなデータを管理するシステムのことです。「いつ」、「どんな商品が」、「何個売れたか」などの情報をためると同時に、在庫管理にも役立てることができます。
POSレジという、POSシステムと接続した据え置き型のレジが長らく主流でした。フィンテック関連の技術開発が進み、専用のレジを購入しなくてもスマートフォンなどにアプリを入れるだけでPOSが利用できるようになりました。
この結果、小売店はレジ導入コストを大きく抑えられるようになりました。コストの面以外でも、キャッシュレス決済など新しい決済方法に柔軟に対応できたり、スタッフの勤怠管理もできたりするのがモバイルPOSのメリットです。
フィンテックに用いられる技術例
今まで見てきた通り、フィンテックはIT技術全般と金融サービスの組み合わせを指します。このため、フィンテックに用いられる技術の幅は広いです。フィンテックに用いられる技術の具体例をいくつか紹介します。
ブロックチェーン
ブロックチェーンとは、情報を鎖のように連ねて複数のネットワークで保存する技術のことで、先ほど紹介した暗号資産を支える基盤技術です。多くのブロックチェーンでは、あらかじめ執行条件をプログラムしておき、その条件を満たした場合に自動的に契約が執行される「スマートコントラクト」という技術が搭載されています。ブロックチェーンの、複数のネットワークが情報を保管する仕組みを「分散管理」といいます。
分散管理やスマートコントラクトの性質から、ブロックチェーン上で執行された契約は「透明性の高さ」や「改ざんの困難さ」といったメリットがあるといわれています。
AI
AI(人工知能)は、厳密な定義はありませんが、コンピュータが膨大なデータを機械学習によって学習して、人間の思考や推論などを人工的に再現する技術全般を指します。フィンテックの文脈では、先ほど紹介したようなロボアドバイザーなどに活用されます。
金融機関の担当者と面談をして資産運用のアドバイスを受けるためには、予約をとって店舗に訪問するといった手間がかかります。サービスにもよりますが、AIによるアドバイスは自宅のパソコンから気軽に利用できるパターンが多いため、今までより気軽に資産運用にチャレンジできるといえます。
API連携
API(Application Programming Interface)連携は、異なるアプリケーションソフト同士を繋ぐ技術のことです。あるアプリケーションからリクエストを送信して、他方のアプリケーションからレスポンスを返します。たとえば、ECサイトでクレジットカード決済をするときなどにAPI連携はおこなわれています。
生体認証
生体認証とは、指紋や静脈などの身体的特徴を読み取ってログインなどの認証がおこなわれる機能のことです。パスワードを入力する方法より、悪意を持った第三者による偽装が難しく、よりセキュリティの高さに優れています。
日本のフィンテックに対する取り組み
フィンテックは、お金を取り扱う対象の性質上、民間のベンチャー企業だけではなく、国の機関や大手金融機関が関わって制度を整えていくことが求められます。国が法的な整備を進めると同時に、普段から利用している大手金融機関がフィンテックのサービスを提供することで、一般の利用者も心理的ハードルが下がり、利用の第一歩を踏み出しやすくなります。ここでは、日本国内の主なフィンテックに対する取り組みについて紹介します。
日本銀行は2016年(平成28年)にFinTechセンターを設立
日本銀行は、金融システムの安定や金融サービスへの信頼確保のため、フィンテックに関する動向の把握・調査・議論を促す場の提供などを目的としたFinTechセンターを2016年に設立しました。欧州中央銀行と共同調査を行い、成果報告書の発表などをおこなっています。FinTechセンターの活動の流れを汲み、2019年以降は中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する実証実験などもおこなわれています。
なお、中央銀行デジタル通貨とは、中央銀行、つまり日本では日本銀行が発行するデジタル通貨のことです。日本銀行によると「現時点でCBDCを発行する計画はないが、決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点から、今後の様々な環境変化に的確に対応できるよう、しっかり準備しておくことが重要」という考えのもと、議論が進められているとのことです。
参照元:https://www.boj.or.jp/paym/digital/rel201009e.htm
金融庁による支援制度の拡充
金融庁によるフィンテック支援制度も拡充しています。金融庁では、フィンテックに関連した事業に取り組みたい民間企業等に対して、事業計画の内容や、どのような届出をするべきかといった個別具体的な相談に応じる「FinTechサポートデスク」を開設しています。
また、フィンテック企業や金融機関が、今までにないフィンテックサービスを開発するにあたっての懸念などを解決できるよう、担当チームを組んでともに実証実験をおこなう「FinTech実証実験ハブ」を2017年から設置し、複数件の実証実験がおこなわれています。このように、革新的なサービスの開発が促進されるよう、サポートを拡充させているほか、ビジネス機会創出のためのイベントや、各国の動向調査も行われています。
三菱UFJ信託銀行株式会社
前項の「金融庁による支援制度の拡充」で紹介した「FinTech実証実験ハブ」の採択案件のひとつが、三菱UFJ信託銀行株式会社による「分散型アイデンティティ(DID)及び検証可能な資格情報(VC)技術を利用した犯罪収益移転防止法上の取引時確認の方法の検証」です。本記事執筆の2025年1月時点で最新の採択案件で、FinTech実証実験ハブ全体を通して9件目の取り組みです。
この取り組みは、三菱UFJ信託銀行株式会社が主催する「DID/VC共創コンソーシアム」の会員企業49社(2024年11月末時点)が検討をおこなってきた、新しい本人確認のあり方に関するスキームです。なお、DIDとVCはそれぞれDecentralized Identifier、Verifiable Credentialの略です。DIDは日本語では「分散型アイデンティティ」、VCは「デジタル証明書」を意味します。
この実証実験では、参加する金融機関が、顧客と契約を結ぶ際に法律上必須の確認事項の結果を顧客自身に提供し、顧客は別の金融機関と契約する際にその確認結果を再利用できる仕組みについての検証をおこなうとのことです。この手法の前提となっている技術がデジタル証明書です。
また、顧客自身が本人確認の結果を所有管理するという概念が分散型アイデンティティであり、複数の金融機関がそれを参照できることによって、何度も同じ本人確認手続きを踏まなければならないという手間を省略できます。こちらの実証実験は、執筆時点でまさに検証中であり、この結果を生かしたサービス開発が今後おこなわれていくことが期待されます。
世界のフィンテック投資額について
世界のフィンテック投資額は、調査機関によって集計定義が異なるため留意して見る必要がありますが、2016年から2022年ころまでは、各国で投資額の大幅な成長が続き、2023年以降は一旦の落ち着きを見せているのが現状です。
金融庁が参照しているアクセンチュアの資料によると、2016年でアメリカが122億ドル、日本が0.65億ドルの投資をおこなっていたそうです。日本もこの時前年比20%増という大きな増え幅ではありましたが、アメリカに対してわずか0.5%ほどの投資額だったことが分かります。
同じアクセンチュアの2018年の調査を更に追っていくと、日本の投資額は5.42億ドルにもなっていることから、数年でいかに成長したかが分かります。世界的には中国の投資額が前年の約9倍にもなったそうです。
参照:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/4th_sangyokakumei_dai4/siryou1.pdf
デジタル業界の発展により様々なX-Techが登場している
金融とIT技術の融合的なサービスのフィンテックを主に紹介してきましたが、IT技術と融合的なサービスが発展しているのは金融業界だけではありません。
フィンテックがFinanceとTechnologyが組み合わされた造語であるように、「ある業界とIT技術の融合的なサービス」の総称を「〜テック」と呼ぶ流れが生まれており、それらをX-Tech(クロステック)といいます。主なX-Techを紹介します。
エドテック(EdTech)
エドテックとは、教育とテクノロジーを組み合わせた取り組みのことです。AIやビッグデータを活用した個別最適化学習、オンライン学習、VR技術による体験型学習など、新しい教育手法を実現します。コロナ禍でその普及が加速し、生徒の学習効率向上と教師の負担軽減に貢献しています。
アグリテック(AgriTech)
アグリテックは、農業とテクノロジーを融合した取り組みで、スマート農業とも呼ばれています。ロボット、AI、IoT技術を活用し、農業の担い手不足や高齢化などの課題解決を目指します。国も2019年から実証実験を行い、作業効率化や生産性向上に向けた取り組みを推進しています。
メドテック(MedTech)
メドテックは、医療とテクノロジーを融合した新しい技術やサービスの総称です。AIを活用した創薬開発やオンライン診療など、様々な分野で展開されています。厚生労働省も医療系ベンチャー企業への支援を通じて、その発展を後押ししています。
ブロックチェーンとフィンテックの関係性
ブロックチェーンは、前述の通り「ブロック」と呼ばれる情報の塊をチェーンのようにつなぎ、複数のネットワークで分散管理する技術です。暗号資産はブロックチェーン内で使えるように作られています。暗号資産自体を売買することができるほか、ブロックチェーン上で契約などの各種操作をするときの手数料として必要でもあります。
フィンテックはブロックチェーンだけを指さない
フィンテックとよばれるサービスにはすべてブロックチェーンが関わっているかというと、そうではありません。
先述したように、フィンテックはIT技術全般と金融サービスの組み合わせをさすため、ブロックチェーン以外の技術が使われているものも多くあります。たとえばPFMでは銀行口座と家計簿アプリ間のAPI連携、銀行アプリにログインする際には指紋認証や顔認証といった生体認証が用いられています。
ブロックチェーンは利用者保護も重視されている
ブロックチェーン・暗号資産の分野は技術開発のスピードが速く、日々さまざまな新規サービスが生み出されています。一方で、利用者が安全に利用するための課題も複数指摘されています。
そのため、個人情報保護、価格の乱高下などからの投資家保護、マネーロンダリング対策、法律上の権利関係の整備など、さまざまな観点での議論が進んでいます。暗号資産は世界的な規模で盛り上がりを見せていることもあり、フィンテックのいちサービスという枠を超えて、新しい通貨としてのあり方が模索されているといえます。
まとめ
本記事では、フィンテックとブロックチェーンの関連性や、それらに関する周辺知識の紹介をおこないました。フィンテックとはFinanceとTechnologyを組み合わせた造語で、一般的にはIT技術を活用した金融サービス全般をさす言葉です。
一方ブロックチェーンは、分散型台帳という、情報のブロックを鎖のようにつないで管理していく比較的新しい技術であり、ブロックチェーン上の通貨の暗号資産はフィンテックのひとつと分類されることがあります。
なお、ブロックチェーンを用いたフィンテックビジネスについて詳しく知りたい方は『ブロックチェーンの活用事例を紹介!ビジネスで活用するメリットは?』をご覧ください。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- ブロックチェーンの専門家に事業のコンサルティングを受けたい
- 既存のフィンテック事業にブロックチェーンを用いて拡大させたい
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

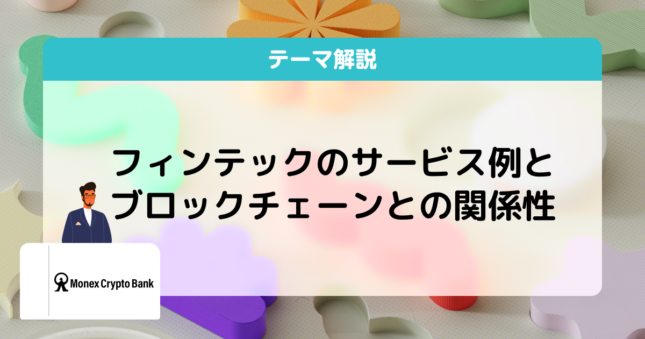

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




