インターネットの進化は、今また新たな転換点を迎えています。近年、メディアやビジネス界で頻繁に取り上げられる「Web3」は、単なるトレンドワードを超えて、デジタル社会の未来を形作る重要な概念として注目を集めています。
インターネットは「Web1」から「Web2」へと発展を遂げ、そして今、ブロックチェーン技術を基盤とした「Web3」という新たなステージへと移行しつつあります。この革新的なテクノロジーは、デジタル資産の取引や金融サービスに革命的な変化をもたらし、従来では実現できなかった新しい経済活動を可能にしています。
本記事では、各世代のウェブの特徴を比較しながら、Web3がもたらす可能性と具体的な活用事例について、わかりやすく解説していきます。
Web1とは
Web1とは、世界中のサイトをインターネットを経由して閲覧できる仕組みが普及し始めた1990年代半ばから2000年代半ばまでの期間のことです。
Web1では、Webページを作成するための言語であるHTMLを用いたテキストサイトが主流でした。この頃はまだ画像や動画は少なく、閲覧者はおもにテキストを見たり読んだりするのみに留まりました。
Web1では、情報発信ができるのはごく一部の人に限られていて、情報の送り手と受け手が固定されていました。当時のインターネットのおもな使い道は、企業や個人が作ったホームページをユーザーが閲覧することでした。
Web1の時代でも電子メールでのやり取りは可能でしたが、インターネット上での双方的なコミュニケーションの実現はほぼ不可能な状態でした。
Web2とは
2005年頃から始まったWeb2の時代は、インターネットの民主化という大きな転換点をもたらしました。それまで情報の受け手に過ぎなかった一般ユーザーが、SNSやブログを通じて自由に情報を発信できるようになり、双方向のコミュニケーションが実現したのです。X(旧 Twitter)やInstagram、Facebook、YouTubeといったプラットフォームの登場により、テキストだけでなく、画像や動画による表現も一般に普及しました。
この革新的な変化は、私たちの日常生活に大きな利便性をもたらしました。多様なサービスを無料で利用できるようになり、情報へのアクセスや発信の自由は格段に向上しました。しかし、この発展は新たな課題も生み出すことになります。
Google、Meta(旧 Facebook)、Amazon、Microsoft、Appleといった巨大テクノロジー企業への権力の一極集中が進み、ユーザーの個人情報が特定の企業サーバーに集約される構造が形成されました。この中央集権的なシステムは、二つの重大な問題を提起しています。
一つは、ユーザーデータの商業的な利用による利益の偏在化、もう一つは、データの一極集中がもたらすセキュリティリスクです。こうした課題は、次世代のインターネットの在り方を考える上で重要な転換点となっています。
Web3とは
インターネットの進化は、Web2で露呈した中央集権化の課題を克服する新たな段階へと突入しています。この次世代のインターネット構想「Web3」は、ブロックチェーン技術を基盤とした革新的なエコシステムを構築し、ユーザー主導の分散型ネットワークという新しいパラダイムを確立しようとしています。
Web3の核心は、データの管理方法の根本的な変革にあります。従来の中央集権的なサーバーによる管理から脱却し、複数のコンピューターによる分散型のデータ保持システムを採用することで、個人が自身のデータを直接管理できる環境を実現します。この技術革新により、ユーザーは特定のプラットフォームに依存することなく、自律的にデジタル資産を運用できるようになりました。
さらに、Web3は経済活動の形態も大きく変えようとしています。ブロックチェーン技術を活用することで、仲介者を必要としない直接的な取引が可能となり、暗号資産取引や資産の所有権管理、スマートコントラクトによる契約の自動執行など、新しい経済活動の地平を切り開いています。この変革は、Web2時代の情報管理の制約から個人を解放し、真の意味でのデジタル主権を実現する可能性を秘めています。
Web3の特徴
特徴1.分散性
Web3は、プラットフォームなどの中央の権威によるコントロールを受けません。ユーザーに権利が分散されるという特徴があります。中央集権型のサーバーや仲介者が不要なため、個人同士の直接的なやり取りが可能です。
またWeb3では、端末同士を直接接続して情報交換をおこなうので、プラットフォームに個人情報を提供する必要がありません。そのため、個人情報の漏えいやサイバー攻撃などのセキュリティリスクを軽減できるのです。
特徴2.自動化(オートメーション)
Web3の根幹であるブロックチェーンには、スマートコントラクトという自動化の仕組みがあります。スマートコントラクトを使用すれば、人の手を介さずに契約を自動で実行可能です。
このような自動化の仕組みは、ブロックチェーン技術を活用した分散型アプリ内でも活用されています。契約や取引の自動化により、暗号資産の売買や不動産取引などさまざまな場面で効率化を実現しています。
特徴3.越境が可能
Web2のようにプラットフォームを経由するやり取りでは、国内に限定されたコンテンツの売買が主流でしたが、Web3では越境が可能です。
越境を可能にしたのは、「DApps」という分散型のアプリです。DAppsを使うと、海外のユーザーとも直接やり取りがおこなえます。
特徴4.プライバシーの保護
Web3ではプラットフォームに個人データを共有する必要がありません。個人が自分のデータを管理できるため、プライバシーの保護が強化されます。中央集権型のWeb2の問題点でもあった、データの流出や情報漏えいなどのリスクを防げるようになりました。
Web3の実用例
ブロックチェーン技術を基盤にしたWeb3の実用例を紹介します。
実用例1.暗号資産
暗号資産とは、インターネット上で流通している電子的な資産のことです。国家によって発行された円やドルなどの法定通貨とは異なり、特定の管理者が存在しないものが多いのが特徴です。
暗号資産は、ブロックチェーンによって管理されているため、銀行などの第三者を介さずに資産のやり取りができます。ネットワーク上の参加者同士で資産の取引データを承認し合って、取引記録の改ざんを防いでいます。
実用例2.DeFi
DeFi(分散型金融)とは、融資や投資などを仲介者なしに実現する仕組みを指します。
DeFiではブロックチェーン技術を使うことで、個人同士の直接的なやり取りが可能です。そのため、金融機関などの中央集権型の機関による金融サービスに比べて、手数料などのコストを削減できます。
実用例3.NFT
NFT(非代替性トークン)とは、ブロックチェーン上に保存されるデジタル資産のことです。とくにアートやゲームなどの業界で人気が高まっています。
NFTではデジタルアートや動画、音楽や音声などのデジタルデータの所有権と信頼性の証明が可能です。
NFTは識別子を持っているため、別のNFTと区別されています。識別子とは、ほかのものと区別するための数字や記号のことです。例えば、宝くじには組数と番号が記載されています。これと同じく、NFTにもそれぞれ固有の識別子が盛り込まれているので、唯一性があります。
NFTを活用することで、コピーが容易なデジタル資産でも、本物とコピー品を区別することができます。デジタルデータを所有していることの証明が可能になり、デジタル資産の収集や売買ができるようになりました。
実用例4.DID
デジタル社会における個人情報保護の重要性が高まる中、Web3の重要な構成要素として「分散型ID(DID:Decentralized Identifier)」が注目を集めています。この技術は、個人情報管理の在り方を根本から変革し、ユーザー自身が完全な主導権を持つ新しいデジタルアイデンティティの仕組みを提供します。
従来のデジタルIDシステムでは、各サービスプロバイダーが独自にIDを発行し、その管理権限を保持する構造が一般的でした。これは個人情報が複数のプラットフォームに分散され、各社の管理方針に委ねられることを意味していました。
しかしDIDは、この従来型の中央集権的な管理構造から脱却し、個人が自身のデジタルアイデンティティを直接管理できるようにします。
DIDの実用化がもたらす可能性は広範に及びます。オンラインサービスへのログインから、行政手続きにおける本人確認まで、あらゆるデジタル認証のプロセスがより安全かつ効率的になることが期待されています。
例えば、住民票の取得やパスポートの申請といった公的手続きにおいても、よりスムーズで信頼性の高い認証が可能となり、個人情報の保護と利便性を両立した新しいデジタルサービスの展開が見込まれています。
実用例5.RWA
現実世界の資産(Real World Assets:RWA)のデジタル化が、投資の概念を大きく変えようとしています。ブロックチェーン技術を活用したトークン化により、従来は取引が困難だった実物資産を、デジタル上で柔軟に売買・管理できる時代が到来しています。
このイノベーションの最大の特徴は、資産の民主化にあります。例えば、高額な不動産投資は従来、一部の富裕層にしか手の届かないものでした。しかしRWAによって、不動産をデジタルトークンとして細分化することが可能となり、より多くの投資家が少額から参加できるようになりました。これは、資産運用の機会を広く一般に開放する画期的な変革といえます。
さらに、ブロックチェーン技術の特性を活かし、すべての取引履歴と所有権情報が改ざん不可能な形で記録されます。この透明性と追跡可能性は、従来の資産管理システムでは実現できなかった高度なセキュリティと信頼性を提供します。これにより、不正行為の防止や個人情報保護が強化され、より安全な資産取引のエコシステムが実現されつつあります。
実用例6.NFTゲーム
デジタルゲームの世界に革新的な変化をもたらしているNFTゲームは、従来のゲーム体験に経済的価値を付加した新しいエンターテインメントの形態です。ブロックチェーン技術を基盤とするこのプラットフォームでは、プレイヤーの活動が実際の経済価値を生み出し、ゲーム内で獲得したデジタル資産を現実の資産として運用することが可能になります。
特徴は、ゲーム内で獲得したアイテムや土地、キャラクターなどが、固有の価値を持つNFT(非代替性トークン)として発行される点にあります。これらのデジタル資産は、専用のマーケットプレイスを通じてプレイヤー間で自由に取引することができ、その価値はプレイヤーのスキルや市場の需要によって決定されます。
さらに、ゲームプレイそのものが報酬を生み出す仕組みも導入されており、キャラクターの成長や達成度に応じて暗号資産が付与されます。これにより、エンターテインメントとしての楽しみと経済的なインセンティブが融合した、新しい形のデジタル体験が実現されています。
まとめ
Web1・Web2・Web3の違いや、Web3の特徴と実用例について詳しく解説しました。
インターネットの歴史は、閲覧専用のWeb1、双方向の情報配信が可能になったWeb2、そしてプラットフォーム経由せずに個人情報が管理できるWeb3へと進化してきました。
Web3の特徴として、スマートコントラクトによって契約を自動で実行できるという点や、仲介者を介さないためプライバシーが守られるという点があげられます。
このような仕組みによって、暗号資産の売買や不動産取引などの効率化ができたり、不正アクセスや情報漏えいのリスクを軽減できたりするのです。
ブロックチェーン技術を活用したWeb3は、これからさまざまな場面で利用する機会が増えると考えられています。『Web3事業者必見!Web3企業一覧【日本・海外のトップ企業・スタートアップ18社】』では、注目しておくべきWeb3企業18社をリストアップしています。日本およびグローバルのWeb3企業に関する知識を一気に把握できる内容になっていますので、ぜひご覧ください。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- 「自社の事業にWeb3を組み込みたいが、何から準備していいか分からない。」
- 「ブロックチェーン活用に向けたコンサルティングサービスを探しているが見つからない」
など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

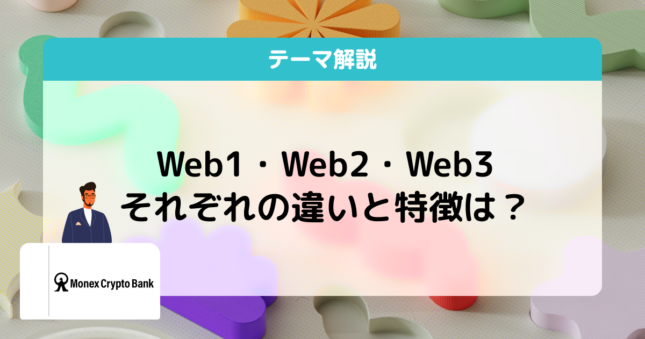

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




