NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)は、ブロックチェーン上で管理することにより唯一性を確保できるデジタルデータです。NFTによって唯一性を与えられたデジタルデータは複製品と区別できるため、独自の資産価値を持つようになります。この特性を活かし、現在はデジタルアートやオンラインゲームなどに使用されています。
しかし、NFTは比較的新しい技術のため、法的な整理・検討がまだ十分にされていません。この記事ではNFTを扱う際に問題となりうる法規制について紹介します。
目次
NFTは暗号資産に該当する?資金決済法
NFTは、基本的には暗号資産に該当しないとされています。資金決済法における暗号資産の定義は次のとおりです。
”資金決済法第2条第14項第1号及び第2号”
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。一物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
1号暗号資産はビットコインやイーサリアムなど、いわゆる暗号資産と呼ばれるものが該当します。NFTは決済手段としての機能を有していることがほとんどなく、1号暗号資産には該当しません。
2号暗号資産についても、1号暗号資産と同等の決済手段等の経済的機能を有していなければ暗号資産には該当しません。NFTに関するものと明記はされていませんが、金融庁のガイドラインで一定の判断基準が示されています。
”金融庁事務ガイドライン(16 暗号資産交換業者関係)”
(注)以下のイ及びロを充足するなど、社会通念上、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまると考えられるものについては、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ものという要件は満たさない。ただし、イ及びロを充足する場合であっても、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまらず、現に小売業者の実店舗・ECサイトやアプリにおいて、物品等の購入の代価の弁済のために使用されているなど、不特定の者に対する代価の弁済として使用される実態がある場合には、同要件を満たす場合があることに留意する。イ.発行者等において不特定の者に対して物品等の代価の弁済のために使用されない意図であることを明確にしていること(例えば、発行者又は取扱事業者の規約や商品説明等において決済手段としての使用の禁止を明示している、又はシステム上決済手段として使用されない仕様となっていること)
ロ.当該財産的価値の価格や数量、技術的特性・仕様等を総合考慮し、不特定の者に対して物品等の代価の弁済に使用し得る要素が限定的であること。例えば、以下のいずれかの性質を有すること
・最小取引単位当たりの価格が通常の決済手段として用いるものとしては高額であること
・発行数量を最小取引単位で除した数量(分割可能性を踏まえた発行数量)が限定的であること
なお、以上のイ及びロを充足しないことをもって直ちに暗号資産に該当するものではなく、個別具体的な判断の結果、暗号資産に該当しない場合もあり得ることに留意する。
出典:金融庁 事務ガイドライン(16暗号資産交換業者関係)P5
ガイドラインによれば、単に法定通貨や暗号資産で売買できるだけでは、暗号資産に該当しないものとされています。ただし、個別具体的な判断を要すると注釈されているため、該当性が不明確な場合は金融庁への相談や照会が必要です。
金融商品取引法
NFTが集団投資スキーム持分にあたる場合、電子記録移転権利に該当し、金融商品取引法の規制を受ける可能性があります。一部例外はありますが、以下の要件に該当すると集団投資スキーム持分は有価証券とみなされます。
- 投資者から金銭等の出資・拠出を受ける
- 出資・拠出された金銭を用いて事業を実施する
- 当該事業から生じる収益等を出資者に分配する
例えばメタバース上の仮想不動産に対する投資を勧誘し、収益を分配する行為は金融商品取引法の規制対象です。NFT保有者に対してインセンティブとして別のトークンを付与する場合なども、有価証券に該当しないか個別に検討する必要があります。
前払式支払手段の該当
発行者など、特定の者に対する支払手段として機能しなければ、NFTは前払式支払手段には該当しません。前払式支払手段は、資金決済法で次のとおり定義されています。代表的なものとして、デパートの商品券やプリペイドカードなどが挙げられます。
”資金決済法第3条第1項”
第三条この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
出典:資金決済法3条1項
物品の購入や役務の提供の代価としてNFTを使用することはほとんどありません。そのため、NFTは前払式支払手段に該当しないことが一般的です。
しかし、ブロックチェーンゲームのアイテムを使って、別のゲームのアイテムを購入できるケースもあります。このような仕組みを構築する場合は前払式支払手段に該当する可能性があるため、慎重な検討が必要です。
為替取引への該当
NFTを対象とした取引を行うこと自体は、為替取引に該当しません。しかし、サービス設計次第では為替取引にあたり、銀行業に該当する可能性があります。
為替取引の定義は法令上明確にされていませんが、最高裁の決定によれば次のものを指します。
”最決平成13年3月12日(刑集55巻2号97頁)”
顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、またはこれを引き受けて遂行すること
NFTを自由に譲渡や払い戻しができる仕組みの場合、為替取引に該当する可能性があるためサービスの構築には慎重な検討が必要です。
景品表示法の規制対象
NFTを景品類として提供する場合は、最高額や総額に規制が及ぶと考えられます。規制の対象となる「景品類」について、景品表示法では次のように定めています。
”景品表示法第2条第3項
3この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
出典:景品表示法2条3項
当該規制はNFT特有の問題ではなく、他の商品を景品として提供する場合と同様です。
賭博罪への該当
NFTをランダムに封入して販売する、いわゆる「ガチャ」方式は賭博罪に該当するとの懸念が示されています。刑法で処罰される賭博の定義は次の通りです。
- 勝敗が偶然の事情により決定されること
- 財産上の利益の得喪を争うこと
ガチャ方式でNFTを販売する行為は、偶然の勝敗によって財産上の利益を得ると言えます。しかし「利益の得喪を争う」点については一概に決められません。NFTの価値の付け方や、得喪を争う主体が誰なのかといった点でさまざまな考え方があるためです。
一方で、海外ではスポーツ選手のプレー動画等をNFT化し、ランダムに封入されたパッケージを販売するビジネスモデルが既に展開されています。こうした状況を踏まえ、関係省庁によるガイドラインの策定が待たれるところです。
「デジタル所有権」という誤解
NFT技術の登場によってデジタルデータは唯一性を担保でき、資産価値を持つようになりました。しかし、デジタルデータをNFT化しても「所有権」は得られません。
NFTは代替不可能な性質を有しており、オリジナルとコピーを容易に区別できます。デジタルアートを物理的に存在する「物」と同じように扱えることから、NFTがデジタル所有権を実現したと評価する声もあります。
しかし、民法上所有権は有体物に対して発生し、データなど形のないものには発生しないとの考えが支配的です。また、NFTについて所有権類似の権利を認める法律も存在しないことから、物権を主張するには法律上の根拠が必要という「物権法定主義」の原則にも適合しません。
NFTの登場により、確かにデジタルデータを他のものと区別して管理できるようにはなりました。ただし、これはブロックチェーン上でデジタルアートを管理することによって発生する特質に過ぎず、法的な権限が付与されるわけではないことに注意が必要です。
なお、NFTを活用したビジネスは下記をご覧ください。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- 「専門家にNFTの企画・設計の相談を行いたい」
- 「NFTの発行サービスの比較を行いたい」
など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

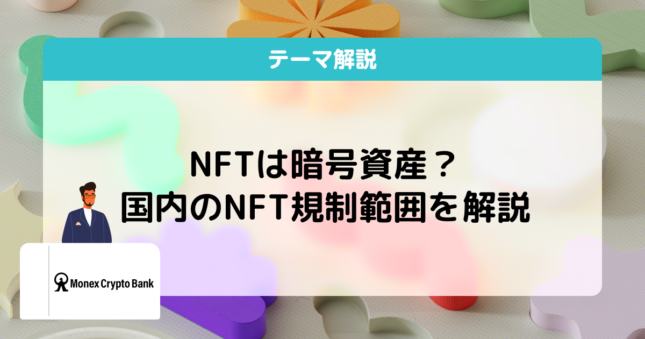

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




