暗号資産の投資は大きな利益を生み出せる可能性がありますが、税金の計算が極めて複雑であるといわれています。
特に、DeFiなどが関係したWeb3関連での投資を行っている場合はその傾向が強く、税務や会計ツールの導入を検討する方や会社も少なくありません。
この記事では、暗号資産で得た利益に対する税金の計算方法や節税対策、損益計算に便利なツールについて解説します。暗号資産にかかる税金の仕組みを知りたい方や、損益計算に苦慮している方はぜひ参考にしてください。
目次
暗号資産の税金は雑所得に分類される
暗号資産の税金は所得税法上雑所得に区分されます。総所得金額に対して累進課税されるため、所得金額が大きくなるほど適用される税率も上がります。
具体的な税率は次の表のとおりです。
| 所得金額(端数切り捨て) | 税率 |
| 1,000円~1,949,000円 | 5% |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% |
| 40,000,000円以上 | 45% |
所得税率は最大45%で、住民税の10%を合わせると55%になります。例えば1億円の利益を得た場合、5,500万円を税金として納める必要があります。翌年の税金が払えなくなる恐れがあるため、利益を得たら納税分を別に保管するなどの対策をしておきましょう。
また、暗号資産は総合課税であり、他の所得と合算して税計算が行われます。一方で、株式の所得は譲渡所得や配当所得に該当し、申告分離課税制度を利用できます。申告分離課税の税率は所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%と、総合課税に比べて低いです。
暗号資産と株式で適用される税制の違いは、制度設計の違いによるものと言われています。しかし、暗号資産の実態を踏まえた税制とするため、分離課税を適用するよう日本暗号資産ビジネス業界から要望が上げられているところです。
暗号資産取引による利益が20万円を超える場合は確定申告が必要
暗号資産取引による利益が20万円を超える場合は確定申告が必要です。課税タイミングは「利益が確定したとき」とされています。
課税対象となるタイミングは、以下の4つのケースで利益が確定したと判断された時です。
- 暗号資産を法定通貨(円など)に売却したとき
- 暗号資産で商品やサービスを購入(決済)したとき
- 暗号資産を他の暗号資産と交換したとき
- マイニング等により暗号資産を獲得したとき
暗号資産を売却したときだけでなく、商品の購入や他の暗号資産に交換した場合も課税される点に注意が必要です。
また、下記は重要な注意点です。
- 含み益について
- 暗号資産を保有しているだけの状態での値上がり(含み益)は課税対象外です。実際に売却や交換などを行った時点で課税対象となります。
- 損失が出た場合
- 確定申告で損失を申告することができます。
- A通貨での利益が100万円
- B通貨での損失が30万円
- → 課税対象は70万円(100万円 – 30万円)
- ただし、給与所得など他の所得との損益通算はできません。翌年以降への繰越控除もできません。
- 確定申告で損失を申告することができます。
- 記録の保管
- 取引履歴や損益計算の根拠となる資料は必ず保管しましょう。特に取引所をまたぐ取引は正確な記録が重要です。
より詳細な具体例を知りたい方は、国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」をご覧ください。
また、個人の場合は利益を確定した段階で課税されますが、法人は決算時に含み益があれば課税対象となります。詳しくは『法人は含み益も課税される点に注意』をご覧ください。
暗号資産の税金未払いはバレる可能性がある
暗号資産取引による所得の申告漏れは、税務調査により発覚する可能性があります。暗号資産で個人が大きく稼ぐ事例が増えてきたこともあり、法人だけでなく、個人に対しても税務当局の監視が強化されています。国外の取引所を利用したとしても、租税条約を締結している国であれば取引履歴を把握できます。
税務署から無申告を指摘されると、以下の税率で無申告加算税が付与されます。
| 本来の納税額 | 割合 |
| 500,000円以下 | 15% |
| 500,000円を超える部分 | 20% |
参考:国税庁タックスアンサー「No.2024確定申告を忘れたとき」
納税義務者が申告期限に遅れて確定申告を行った場合でも、納付すべき税額の5%が加算税として課される場合があります。より深刻なのは、まったく申告を行わないケースです。税務調査により無申告が発覚した場合、基本的に納付すべき税額の15%(50万円超の部分は20%)に加えて、さらに10%が加算されます。
さらに、所得を意図的に隠ぺいするなど、特に悪質なケースでは40%の重加算税が課されます。たとえば、本来の納税額が50万円の場合、重加算税として20万円が追加され、合計70万円の納税が必要となる可能性があります。
このように、確定申告を行わないことで一時的に納税を回避できたとしても、発覚時には多額の追加負担が発生します。近年では、国内外の取引所との情報連携や国際的な課税情報の交換により、税務当局による取引把握の精度が向上しています。
結論として、適切な時期に正確な確定申告を行うことが、長期的に見て最も賢明な選択となります。
確定申告の方法や税額の計算について不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
暗号資産の税金計算時の3つのポイント
暗号資産に関する税金の計算方法として、知っておくべきポイントが3つあります。
- 総平均法を使用する
- 損益通算や赤字繰越ができない
- 時価相当額に換算される可能性がある
1. 総平均法を使用する
暗号資産取引による所得を算出する際、個人の場合は原則として総平均法を使用します。総平均法は、基準期間内における暗号資産の平均購入価格と、売却価格の差額で所得を算出する方法です。
例えば、1年間で次のような取引履歴があったと仮定します。
- 1月:1単位あたり300万円で5単位購入
- 4月:1単位あたり350万円で4単位売却
- 7月:1単位あたり330万円で5単位購入
- 10月:1単位あたり400万円で3単位売却
まずは合計購入価格を合計購入数で割って、平均購入価格を算出します。今回の場合、平均購入価格は315万円です。
- 1年間の合計購入数:10単位
- 1年間の合計購入価格:300万円×5単位+330万円×5単位=3,150万円
- 平均購入価格:3150万円÷10単位=315万円
次に、合計売却価格を算出します。今回の事例で計算すると、2,600万円です。
- 1年間の合計売却数:7単位
- 売却価格:350万円×4単位+400万円×3単位=2,600万円
最後に合計売却価格から、平均購入価格に売却数量をかけた価格を引くと所得が計算できます。今回の場合は、395万円が暗号資産取引によって得た所得として扱われます。
- 2,600万円 - 315万円 × 7単位 = 2,600万円 - 2,205万円 = 395万円
なお、総平均法による所得計算では、期間内の全取引を通じた平均取得価額を基準とするため、個々の取引での損益とは異なる結果になる場合があります。売却時の価格が平均取得価額を下回れば損失が発生し、上回れば利益が発生します。
例えば、
- 平均取得価額:315万円
- 売却価格:300万円
- →1単位あたり15万円の損失
このように、総平均法では実際の損益を適切に反映した計算が行われます。ただし、複数の取引所での取引がある場合は、すべての取引を合算して計算する必要があります。
なお、暗号資産レンディングによる利益の計算方法は『暗号資産(仮想通貨)レンディングでの利益の計算方法』を、DeFi全般に関する税金の基礎は『DeFiに関する税金の基礎知識』をご覧ください。
2. 損益通算や赤字繰越ができない
暗号資産で得た取引は、損益通算ができません。たとえ暗号資産による利益がマイナスだったとしても、給与所得や事業所得と相殺することは不可能です。
また、赤字を翌年度以降に繰り越せないのも特徴です。例えば1年目の利益が300万円の赤字で、2年目が500万円の黒字だったときに、相殺して200万円の黒字とすることはできません。損失は考慮されず、単年度の利益に対して課税されます。
株式の場合は3年間赤字繰り越しができるため、扱いを混同しないようにしましょう。
3. 時価と著しく異なる取引への注意点
暗号資産を時価よりも著しく低い金額で取引した場合、税務上、実際の取引価額ではなく時価で評価される可能性があります。
これは、取引の経済合理性や実態に基づいて判断されます。
例えば、時価100万円相当の暗号資産を著しく低い価額(例:20万円)で取得した場合、その差額(80万円)については、贈与税の対象となる可能性があります。
同様に、著しく低い価額で売却した場合も、実際の売却額ではなく時価で評価され、課税関係が生じる可能性があります。 特に以下のような取引の際は注意が必要です。
- 知人や関係者との相対取引
- 市場価格から大きく乖離した価格での取引
- 贈与や遺贈
など、無償での暗号資産の移転 このような取引を行う場合は、取引時の適正な時価の記録を残し、必要に応じて税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
特に贈与に該当する可能性がある場合は、所得税だけでなく贈与税の課税関係も検討しましょう。
暗号資産税金計算ツール4選
暗号資産の所得や税計算は複雑で、取引数が多くなるほど管理も難しくなります。そこで、暗号資産の税金計算をアシストする税金計算ツールを4つ紹介します。
- クリプトリンク
- クリプタクト
- defitact
- 暗号会計RIKYU
無料お試し期間が設定されているツールもあるため、毎年税計算に苦心している方は参考にしてください。
1. クリプトリンク

クリプトリンクは取引所のデータを登録すれば収支計算結果を生成できるツールです。国内外の暗号資産取引所の計算に対応し、会計ソフトとの連携も簡単に設定できます。
複数の取引所を利用している方、帳簿付けの仕方がそもそもよくわからない方におすすめです。14日間の無料トライアル期間があるため、使い心地を試してみてはいかがでしょうか。
2. クリプタクト

クリプタクトは、取引履歴をアップロードすれば自動で損益計算ができます。暗号資産の価格データを1分単位で採用しているため、リアルタイムで資産価値を把握することが可能です。そのほか、DeFiやNFTを自動識別できる点が特徴として謳われています。
フリープランでも、取引所の自動対応機能や取引の自動識別機能を利用でき、50件までなら損益計算結果も表示されます。ポートフォリオも簡単に作成できるため、適切な資産管理を行いたい方におすすめです。
3. defitact

defitactは、ブロックチェーン取引を見える化する「Web3の家計簿」です。複数のブロックチェーンを利用していても、defitactを使用すれば簡単に一元管理できます。
また、スマホでも見やすいように、モバイルファーストのデザインを優先しているのが特徴です。膨大で複雑なデータをできるだけ簡単に管理できるよう、ユーザー目線の機能開発を信条としています。
日本語だけでなく英語にも対応しているため、グローバル環境で使用する方にもおすすめのサービスです。
4. 暗号会計RIKYU

暗号会計RIKYUは、法人向けの暗号資産会計システムです。異なるブロックチェーンの複数ウォレットを一元管理できます。
ウォレットアドレスを登録するだけで損益計算と仕訳を行い、会計システムへの連携も可能です。金銭的価値のない取引履歴は自動で除外する機能まで搭載されています。
プランはウォレット数や取引数に応じて選べます。アカウントを作成すれば無料でお試しできるため、法人向けのツールを探している方は一度試してみてはいかがでしょうか。
暗号資産関連の税金は今後も改正される見込み
暗号資産に関する税制は、登場時から現在に至るまで次のような改正が行われてきています。
| 年 | 主な内容 |
| 2014年 | 暗号資産が政府答弁でモノと認定され、消費税の課税対象となる |
| 2017年 | 暗号資産が資金決済法上の支払手段と位置づけられ、消費税非課税になる |
| 2019年 | 暗号資産が法人税期末時評価の対象に加わる |
| 2023年 | 自己発行の暗号資産が法人税期末時評価から除外される |
一般社団法人日本暗号資産取引業協会や一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会などの業界団体は、暗号資産に関する税制や法規制の改正を政府に要望しています。2025年も引き続き税制改正が行われる見込みです。
暗号資産は登場して日が浅いため、今後も国際動向や経済状況を踏まえながら、税制の改正は続くと考えられます。
暗号資産の2つの税金対策(節税対策)
個人のまま暗号資産取引を行う場合、税制が変わらない限り効果的な節税対策はありません。しかし、次のような手段により、そもそも適用される税率を変えたり、課税タイミングを調整したりすることはできます。
- 法人化する
- 利益確定のタイミングを調整する
順番に解説します。
1. 法人化する
法人化すると、暗号資産取引利益にかかる税金は所得税ではなく法人税が課せられます。法人の場合、基本税率23.2%に地方税等が加算され、実質的な税負担は約30%程度となります。一般的には、800万円以上の利益を得られるようになったら法人化を検討するタイミングと言われています。ただし、法人化の判断は税率だけでなく、経営管理コストや社会保険の必要性など、総合的な検討が必要です。
法人化について詳しく知りたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。
2. 利益確定のタイミングを調整する
暗号資産の利益に課税されるタイミングは、利益確定時です。売却や決済などを行わない限り、既に保有している暗号資産に対しては課税されません。
給与所得者や年金受給者は、雑所得が年間20万円までであれば非課税です。つまり、20万円前後の含み益が見込まれる場合、20万円を超えない範囲で利益確定すれば課税を避けられます。ほかにも、適用税率が上がる直前の金額に抑えるといった方法も有効です。
これらの税務計画は、投資家が利益を最適化するための正当な戦略として活用できます。
まとめ
暗号資産の損益計算や税計算は複雑なうえ、所得の算出誤りや、取引の計上漏れがあると後から追徴課税されるリスクがあります。確定申告の前に慌てて計算しなくて済むように、日ごろから取引を正確に管理しましょう。
しかし、取引数が多かったり、複数の取引所を利用していたりすると、正確な把握は困難です。紹介した計算管理ツールを活用すれば、手作業で行うよりもミスや手間を減らせます。不安な方は税理士に相談するのもおすすめです。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- 「暗号資産の税務に関するツールを導入したい」
- 「DeFiでの複雑な会計を一括で解決できるソリューションを探したい」
など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

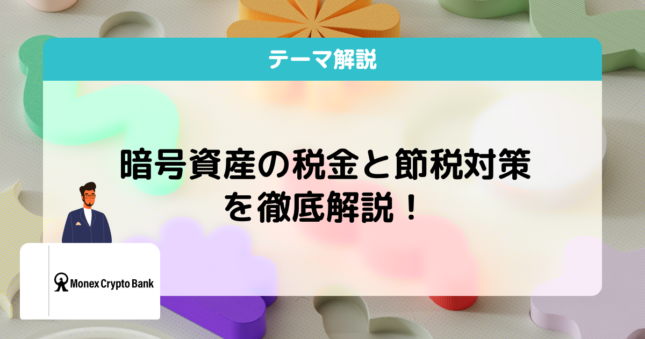

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




