2010年代からたびたび世界的な盛り上がりを見せてきた暗号資産(仮想通貨)。価格の変動を繰り返しながら、日々さまざまなサービスが開発され、暗号資産でできることは増えてきています。そんな暗号資産について、もっとよく知りたい方も多いのではないでしょうか。
この記事では、暗号資産の仕組みを支える「マイニング」について解説します。
目次
暗号資産(仮想通貨)・ビットコインのマイニングとは
暗号資産(仮想通貨)におけるマイニングとは、簡単にいうと、取引の正当性を確認し、その内容をブロックチェーンの一部として記録し、その貢献に対して報酬を得る行為のことです。
ブロックチェーンとは、データをブロックという塊にまとめ、それを鎖状につないで保存していく技術のことです。マイナー(採掘者)と呼ばれる参加者がマイニングをおこなうことで、ビットコインのようなPoW(プルーフ・オブ・ワーク)と呼ばれる仕組みを採用するブロックチェーンが成立しているといえます。
まずは「マイニング」という言葉の由来から、順を追って解説します。
暗号資産以外の「マイニング」
マイニング(mining)という言葉は暗号資産が生まれる前から存在します。マイニングという言葉はどういった文脈で、どのような意味で使われてきたのでしょうか。
鉱山での採掘
「マイニング」という言葉で辞書を引いて最初に出てくるのは、鉱山での採掘という意味です。鉱山で大量の岩石や土砂のなかから、ほんのわずかの鉱物を探し出します。
このように、時間や労力をかけて貴重な資源を見つけ出す過程が「採掘」と呼ばれ、その成果に大きな価値が生まれます。
データマイニング
鉱山の採掘の次に「マイニング」が使われるようになったのは、「データマイニング」というデータを探索する行為です。
コンピュータが広く普及して以降、1990年代ごろから、膨大なデータを統計や機械学習を用いて処理し、有益な法則性などを見つけ出す技術が注目されるようになりました。
このことが鉱山での採掘のイメージに重なり、「データマイニング」という言葉が生まれ、一般に知られるようになりました。
ビットコインのマイニングの仕組みとは?わかりやすく解説
ビットコインは、2024年11月時点で最も時価総額の高い暗号資産です。暗号資産とは、一般にブロックチェーン技術によって管理されるデジタル資産のことをいいます。
ブロックチェーンのブロックは「そのブロックに記録したい取引(トランザクション)内容」、「直前のブロックのハッシュ値」、「ナンス」という3要素で構成されています。
ハッシュ値とは、ハッシュ関数という特殊な変換関数を用いて情報を変換した値のことをいい、ナンスは、「number used once」の略で、ハッシュ値を調整するために1度だけ使われる値です。この3要素が合算され、ハッシュ化されることによって、次のブロックにおける「直前のブロックのハッシュ値」として記録されます。
各ブロックの検証と承認、保存の役割を担うコンピュータは、競争を通じて世界中で1台だけが選ばれます。この選出プロセスは、条件に合致するハッシュ値を導き出す競争によって決まります。ランダムなナンス値を繰り返し入力してハッシュ化をおこない、あらかじめ決められた条件を満たすハッシュ値を最も早く発見したコンピュータがブロックを保存することができます。
ランダムなナンス値をひたすら入力して膨大な数のハッシュ値を生成し、その中から正しいナンス値を見つけ出すという様子が、先述の採掘作業を連想させます。
ここから、ビットコインなどのブロックチェーンにおいてブロックを検証や承認、保存する行為のことをマイニングと呼ぶようになりました。
マイニングはPoW型ブロックチェーン向けの用語
実は、マイニングはすべてのブロックチェーンで使われる言葉ではありません。ブロックチェーンでは、従来の中央集権的なデータの管理から脱却し、分散的にデータを管理することを目指しています。
そのなかで、取引の検証と保存は、あらかじめ決められたルールに則っておこなわれます。この事前に決めたルールのことをコンセンサスアルゴリズムとよびます。PoW(プルーフ・オブ・ワーク)というコンセンサスアルゴリズムを採用したブロックチェーンで、データの検証と保存の行為を「マイニング」と呼びます。
PoW型ブロックチェーンの代表格がビットコインです。前述したように、マイニングでは計算競争によって検証や保存をおこなう1台が決まります。言いかえると、参加するネットワークのマシンパワーを駆使してPoW型ブロックチェーンは成り立っています。
PoS型ではステーキングと呼ばれる
コンセンサスアルゴリズムはPoW型だけではありません。ほかのメジャーなコンセンサスアルゴリズムとしては、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)があり、イーサリアムやソラナなどの暗号資産で採用されています。
PoS型ブロックチェーンの承認に参加する行為は、「出資」を意味する英語の「ステーク(stake)」を語源として「ステーキング」と呼ばれます。
イーサリアムは、2022年に「The Merge」という大規模なアップデートを経て、PoW型からPoS型へ移行しました。
PoS型では、暗号資産の保有が承認者を決めるうえで重要な要素となります。わかりやすい具体例としては、その暗号資産を多く所有しているほど承認者に選ばれやすくなるという仕組みが挙げられます。
そして、PoI(プルーフ・オブ・インポータンス)など、PoS型から派生したコンセンサスアルゴリズムも存在します。これらにおいても、出資が承認者選出の要素として含まれる場合は、同じく「ステーキング」という用語が使われます。
マイニングの必要性やメリット
改ざんが難しく、資産としての信頼が高い
ブロックチェーンは、前述の通り取引の情報を鎖状のデータのブロックで繋いで保存する技術です。生成される次のブロックには、前のブロックのハッシュ値が格納されます。このため、仮に悪意のある誰かが取引内容を改ざんしようとすると、次のブロックのハッシュ値も書き換える必要があり、それは次のブロックにも伝播していきます。
この再計算には莫大なマシンパワーが必要であり、改ざんを現実的に不可能にしています。
このようなデータの改ざんの困難さはブロックチェーン全般にいえることです。そして、PoW型ブロックチェーンのマイニングは、この改ざんの困難さをさらに強化しています。
誰かが取引の改ざんを試みた場合、単にデータを改ざんするだけではなく、全てのブロックで計算競争を勝ち抜く必要があります。
この競争は膨大な計算リソースを要し、現実的には実現不可能です。その結果、悪意ある行為よりも正当にマイニングを行い報酬を得る方が効率的な仕組みになっています。
さらに、このマイニングによる堅牢な仕組みは、暗号資産の社会的信用性も高める役割を果たしています。法定通貨のような従来の中央集権的な資産だと、銀行や政府などの公的機関が保証することによって信頼が得られています。
一方、分散型管理のブロックチェーンでは、システムの堅牢さやデータの改ざんの難しさがその信頼を支えています。そのような信頼を背景として、たとえばビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、国際的な送金や資産保全手段として利用されています。
このように、マイニングによって改ざんがさらに困難になることは、暗号資産の価値と信頼性を支える重要な要素となっています。これがマイニングがネットワークの維持に必要な理由です。
ネットワークの分散性とセキュリティを高めている
PoW型ブロックチェーンでは、マイニングを通じて世界中の人がネットワークに参加できます。また、計算競争に勝った場合に得られる報酬をインセンティブとして、参加の動機付け設計がされています。複数のマイナーがネットワークに参加することで分散性が向上し、特定の管理者に依存しない運用を実現しています。
分散性が高いネットワークは、外部からの攻撃や不正アクセスにも高い耐性をもつため、セキュリティも向上します。たとえば、ある攻撃者が一部のマイナーのネットワークを攻撃したとしても、その攻撃対象のネットワークだけが影響を受けます。
このように、マイニングが実現する分散性により、一部のノードやマイナーへの攻撃が成功しても、全体のシステムは堅牢であり、機能し続けることができます。
マイニングの課題やデメリット
マイニングの課題として最も注目が集まっているのはエネルギー消費が非常に大きいことです。マイニングは、マイナーが計算競争をおこない膨大な数のハッシュ値計算をすることで勝者が決まるため、この仕組み上、マシンパワーを駆使することは不可避です。
それに加えて、ブロックチェーンが成熟してくるに従ってマイニングの難易度は上がり、一度の競争において必要となるエネルギー量が増えていくという問題もあります。

出典元:https://ccaf.io/cbnsi/cbeci/comparisons
イギリスのケンブリッジ大学は、ビットコインやイーサリアムの電力消費量への問題提起として、Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI)というサイトを公開し、ブロックチェーンの電力消費量を可視化しています。
その中で、ビットコインの年間電力消費量は、国家ひとつ分の消費量にも匹敵するという驚くべき情報も記載されています。

出典:https://ccaf.io/cbnsi/cbeci/comparisons
具体的には、2024年11月時点では、エジプト・アラブ共和国やポーランドの年間消費量よりもビットコインの年間消費量の方が多いことが示されています。環境問題への関心が高まっている昨今において、マイニングの電力消費量の問題は、暗号資産所有者だけではなく、社会全体の課題としても認識されつつあります。
しかし、別の捉え方をすると、電力というコストだけでネットワークの分散性が保たれているともいえます。従来の中央集権的なシステムには管理者が不可欠で、それによるデメリットを克服するために分散管理の概念が生み出されました。これが電力量費だけで実現できているということは、ネットワークの管理手法という観点ではメリットともいえます。
解決策としてPoSが誕生した
PoWの電力消費量問題への解決策として考え出されたのが、先ほど紹介したPoSというコンセンサスアルゴリズムです。トークンの保有量やその他の条件によって承認者が決まるため、莫大な計算をする必要がなく、電力量を大幅にカットすることができます。
この結果、エネルギー効率が格段に向上し、PoWと比べて環境負荷を下げる利点があります。
一方で、トークンの保有量によって承認者が決まりやすい場合、承認者が特定の人に偏りやすくなり、中央集権化することが懸念されます。
この懸念への対策として、多くのPoS型ブロックチェーンではランダム性などの調整アルゴリズムを採用しています。一部の実装では、一度承認者になった場合は承認者になりづらくなるように当選確率を調整するなど、分散性が維持できるよう工夫されていますが、各ブロックチェーンにおいて課題は散見されます。
個人が参入しにくく分散性が低下する
マイニングのデメリットとして、個人が参入しにくく分散性が低下するという点も挙げられます。
マイニングに必要な計算は、電力を大量に消費するわけですが、そもそもマシンが計算に対応できるスペックでないと、参加することすらできません。
近年では、大規模な資本を持つ企業がマイニングを事業としておこなっています。これに対して個人が同程度のスペックのマシンを用意するのはハードルが高い状況で、マイニングによって稼ぐよりは暗号資産を直接売買する方が経済的であると判断されることが多いようです。
このため個人のマイナーの数は減少傾向にあり、マイニングは分散性を維持する仕組みではありますが、実質的には分散性が低下するデメリットも持っています。
マイニングの半減期とは
マイニングによって得られる報酬は、「トランザクション手数料」と「マイニング報酬」との2種類があります。
トランザクション手数料は、ブロックに取り込んだ契約に設定してある手数料のことです。マイナーは、少しでも高い利益を得たいため、高めの手数料が設定してある取引からブロックに取り込んでいくことになります。このため、取引を早く行いたい人は、この手数料を高めに設定しておくことで早めに取引を締結しやすくなるのです。
一方、マイニング報酬は、新しいブロックを生成したことに対して支払われる報酬で、ブロック報酬とも呼ばれます。
そのマイニング報酬には、「半減期」という、報酬額が半分になるイベントが設定されています。具体的には、当初のマイニング報酬は50BTCでしたが、2012年11月28日に25BTCになり、2016年7月9日に12.5BTCになり…と半減を繰り返し、2024年4月20日には3.125BTCになりました。半減期は、前回の半減期から21万ブロックが生成されたタイミングと決められており、約4年で半減期が来るとされています。
ビットコインの発行上限は2,100万BTCと決まっており、2140年頃に新規発行が終わるといわれています。この将来的に訪れる発行上限まで、新規供給量が緩やかに減少していくことを目的として半減期は設定されています。
将来的に報酬がゼロになるわけではない
前項で触れたとおり、マイニング報酬は半減期によって少なくなっていくことが決まっており、2140年頃にはマイニング報酬は無くなるとされています。
では、マイナーはブロックの生成作業で報酬を得られないのか気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
ブロック内に含まれるトランザクションの手数料は払われ続けるため、マイニングによって報酬がゼロになるわけではありません。
マイニングのやり方は? 3つの種類を解説
マイニングについて理解が深まってきたところで、マイニングの詳細にも興味が出てきた方もいらっしゃるかもしれません。マイニングには、主に3種類のやり方があります。ここでは、ひとつずつ概要を説明します。
ソロマイニング
まずはソロマイニングです。ソロマイニングとは、その名の通りひとりでマイニングに取り組むことです。気軽に始められそうな気がしますが、計算競争に勝つためには、高い専門性をもち、高いスペックのマシンを用意する必要があります。マイニングに参加する企業が用意する高性能マシンと計算競争で台頭に戦えるようなPCを個人で用意するのは、現実的には難易度がかなり高いです。
プールマイニング
プールマイニングとは、マイニングプールと呼ばれるマイニングを行う集団に、インターネットを通じて自分のマシンパワーを提供することでマイニングに参加する方法です。
チームメンバーのマシンパワーを集結させるため、ソロマイニングより計算競争に勝てる確率は高まり、安定した報酬を得られやすくなります。
一方で、報酬はチームのメンバーに分配されるため、高額な報酬は期待できません。提供する計算能力に応じて分配量が決まるため、プールマイニングであっても報酬をより高めるためにはマシンスペックは高い方がよいでしょう。
クラウドマイニング
クラウドマイニングは、マイニングを事業としておこなっている企業に出資してマイニングに参加する方法です。報酬は配当金として得られます。
自分自身で高性能マシンを用意する必要もなく、マイニングについての知識を深く勉強する必要もないので、手軽な方法といえます。マイニングに直接参加するというよりは、マイニング企業に投資するといったイメージの方が近いかもしれません。
クラウドマイニングは詐欺にも注意
クラウドマイニングは詐欺にも注意しましょう。たとえば、存在しないマイニングプロジェクトをうたって資金を集め、その資金が持ち逃げされるといった事件も実際に発生しています。マイニング企業に出資する際には十分に調査してから参加するようにしましょう。
マイニングは稼げない?収益性を左右するポイント
マイニング報酬の収益性を左右するポイントについてお伝えします。
暗号資産(トークン)自体の価格
たとえばビットコインのマイニング報酬はビットコインで支払われます。1回のマイニングで得られる報酬は、マイニング報酬とトランザクション手数料と決まっているため、それによって得られるビットコインの価値自体が高ければ、得られる報酬も実質高くなります。
ビットコインなどの暗号資産のボラティリティは法定通貨と比べて大きく、価格推移の予想は難しいですが、暗号資産自体の価格が報酬の収益性を左右するポイントのひとつです。
半減期によるマイニング報酬の変動
半減期を迎えるとブロック報酬とも呼ばれるマイニング報酬が減ることはすでに説明しました。もちろん、トランザクション手数料もあるので、報酬の総額が必ず減るとは言えませんが、マイニング報酬が半分になるので、半減期を迎えると報酬は減る傾向にあります。
一方、マイニングの報酬が減ると、コストに見合ったリターンが得られないため、将来的に暗号資産自体の価格が上昇することを期待して、マイナーはすぐには暗号資産を売らなくなります。
すると、市場に供給される暗号資産の量が減ることになり、市場原理によって暗号資産の価格が上昇することがあります。これが、ビットコインの価格が上昇する理由のひとつとされています。ただし、実際には複合的にさまざまな理由が関係しており、これがビットコイン価格上昇のすべてを説明するものではないことには注意が必要です。
まとめると、半減期によってマイニング報酬は減る傾向にある一方で、半減期がビットコインの価格を引き上げる間接的な要因になっているともいわれます。一概にマイナーにとってよいか悪いかは言い切れませんが、収益性を左右する要素のひとつです。
採掘難易度の変動
マイニングの採掘難易度は、10分に1ブロックが採掘されるようにプログラムで自動的に調整されています。マイナーが増えれば必要な計算力は上昇するので難易度は高くなり、競争に勝つためにはハイスペックなマシンを用意しなければなりません。そのためのコストとマイニング報酬が見合うかどうかはよく検討する必要があります。
電気代の変動
マイニングのためには莫大な計算量が必要です。当然ながらその計算量の多さは電気代にも反映されます。世界情勢などの影響を受けて電気代自体が高騰しているときは、マイニングにかかるコストとしての電気代も高くなることに注意しましょう。
マイニングについてよくある質問
収益性をわけるポイントについて見てきましたが、それ以外にも気になることは多いと思います。マイニングについてよくある質問をまとめました。
Q.マイニングはスマホでできる?
ビットコインの場合、実質できないといってよいでしょう。CPUが搭載されているので参加自体はできますが、スペックの問題で計算競争に勝てる見込みは非常に低いためです。
Q.マイニングはゲーミングパソコンじゃないとできない?
こちらも、ビットコインの場合スマホと同様にスペックの問題で厳しいと考えられます。ゲーミングパソコンを使って参加する場合は複数台を利用していることが多いです。
計算難易度が低い小規模なブロックチェーンであれば1台でもできる可能性があります。
Q.マイニングは電気代が高いって本当?
電気代は高いです。PoWという仕組み上計算量を多く費やすため電気代が高いのは必然である上に、ビットコインだと計算難易度が上昇傾向にあること、世界的な電気代高騰の影響などもあって、マイニングは高額な電気代を必要とします。
Q.マイニングの利益分は税金がかかる?
マイニングの利益分は、雑所得か事業所得のどちらかに分類されます。雑所得と事業所得の区分は、マイニング事業の規模、継続性、事業性の有無などによって判断されるためです。他の収入と同様に確定申告等をおこない納税する必要があります。
まとめ
マイニングはPoW型ブロックチェーンを支える重要な技術である一方、今日では環境問題なども抱えています。特にビットコインでは、マイニングの計算難易度は非常に高くなっており、個人で計算に参入するのはなかなか難しい状況です。
PoWに代わる新しいコンセンサスアルゴリズムとして、PoSなどの新しい仕組みも生まれています。技術革新のスピードは目ざましいものがあるため、今あるコンセンサスアルゴリズムだけではなく、より効率的で堅牢なコンセンサスアルゴリズムの開発が今後も期待されます。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- 「ビジネスにブロックチェーンを活用したいため専門家と相談をしたい」
- 「自社ビジネスに暗号資産やブロックチェーンを組み込む際の比較検討を行いたい」
など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

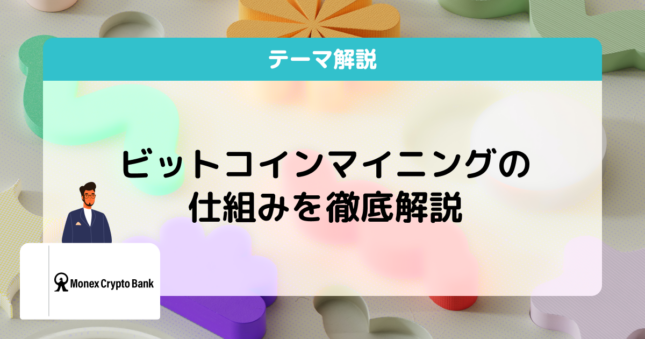

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




