SDGsの目標達成には、世界の人々が平等に金融サービスを受けられるように金融包摂を進める必要があります。金融包摂を実施すれば個人の生活が潤うだけではなく、社会の経済活動が活発になるなどの成果が期待できるでしょう。
とくに、最近ではデジタル技術が進化しました。金融サービスも例外ではありません。インターネットさえあれば、世界中の人々がサービスを受けられるようになるでしょう。
そこで本記事では、金融包摂の定義やメリットについて解説します。また、国内外の金融包摂の事例やデジタル金融包摂サービス(フィンテック)についても触れていきます。
目次 [hide]
金融包摂とは
世界銀行(The World Bank)によると、金融包摂は「すべての人々が、経済活動のチャンスを捉えるため、また経済的に不安定な状況を軽減するために必要とされる金融サービスにアクセスでき、またそれを利用できる状況」と定義しています。経済的に不安定な状況にある人々が、基本的な金融サービスが利用できるように支援するのが金融包摂の目的です。
同団体が2021年に公表したデータによれば金融取引口座の保有率は、世界全体で76%と例年と比較して大きく伸びる結果となりました。しかし、いまだに約3割の人が金融サービスを満足に受けられない状態です。途上国や先進国でも貧困や差別などで銀行口座を持てなかったり、銀行の融資を受けられなかったりする人が一定数いるのが現状です。
出典:世界銀行「コロナ危機で電子決済の利用が世界的に急増」「The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19」
金融包摂の読み方
金融包摂とは「きんゆうほうせつ」と読み、英語では「Financial Inclusion(ファイナンシャル・インクルージョン)」と表記します。社会包摂(社会的に弱い立場の人を排除せずに、社会の一員として取り込む)から派生した言葉です。
包摂という言葉は「取り込む・包み込む」という意味です。SDGs(持続可能な開発目標)の目標10「人々の包摂、公正、平等の推進」にも、包摂という言葉が使用されています。金融包摂は、SDGs達成のためにも重要な役割を果たすことでしょう。
金融包摂の意味と必要性
国連事務総長顧問(UNSGSA)のオランダ・マキシマ王妃によれば「金融包摂は人間開発とエンパワー面そのものであり、人々の生活を改善する手段」だと話をしています。人々が金融サービスを利用すれば、下記のメリットが考えられるとのことです。
- 銀行口座の開設により、商業への投資できる
- 商業で得られた利益は、家族への投資できる
- 子どもが優良な教育を受けられる
- 商業の選択肢が広がる可能性がある
さらに、政府が賃金や年金を支給する際にデジタル金融サービスを活用すれば、大きなメリットがあるといわれています。現金に頼らない支給や、運用コストの削減が可能です。また、支給漏れも大幅に削減できるでしょう。
デジタル金融包摂とは
最近では現金でのやり取りが減り、通帳の数値のみで取引される機会も増えてきました。金融包摂でも、スマートフォン・タブレットを用いて決済や融資をおこなう「デジタル金融包摂」ができる時代になったといえます。
現在、最も注目されている金融デジタル技術は「フィンテック(FinTech)」ではないでしょうか。フィンテック(FinTech)は、金融(Finance/ファイナンス)と技術(Technology/テクノロジー)を組み合わせた造語です。金融サービスとデジタル技術を結びつけたサービスをおこない、金融包摂をサポートします。
フィンテックは既存のシステム(ネットバンキングやオンラインバンキング)とは異なり、オープンバンキングを採用しています。オープンバンキングとは、銀行と外部サービスを連携し、価値ある新サービスを提供することです。身近な例でいえば、銀行口座と会計ソフトをAPI(異なるシステム間でデータ連携する仕組み)によって連携させ、自動仕訳する機能などが挙げられます。
金融包摂とフィンテックの関連性とは
金融包摂はフィンテックの活用で、世界中の人々に経済活動を大きく促せるだけではなく、社会課題を解決できる可能性があります。インターネットに接続さえできればスマートフォンやタブレットを用いて金融サービスなどを利用でき、貯蓄や投資が可能になるでしょう。金融包摂では「フィンテック」が非常に重要であるといえます。
今後、IT技術は目まぐるしい進化を遂げる可能性があります。国外ではデジタル金融サービスが必要不可欠になるシーンが発生するかもしれません。また、国内では少子高齢化の影響で、高齢者に対しておこなうITサービスが多くなることが予想されます。効果的な金融包摂を実施するには、下記のフィンテックを用いて解決すべきでしょう。
<金融包摂に有効なフィンテック>
- API連携:家計簿アプリのように金融機関と外部サービスとを繋ぎ合わせる仕組み
- ブロックチェーン:分散型のネットワークに存在している非中央集権型の仕組み
- 生体認証:個人情報保護やスキミング防止に効果的な仕組み
- AI:ビッグデータと組み合わせて対象者に合ったアドバイスをするツール
ブロックチェーンと金融包摂の関係
ブロックチェーン技術も金融包摂の手段のひとつとして認識されつつあります。ブロックチェーンとは、特定の管理者不在のネットワーク(P2Pネットワーク)上に存在する「仕組み」です。
ブロックチェーン技術が金融包摂の分野で注目を集めている理由の一つに「DeFi(分散型金融)」があります。DeFiは、ブロックチェーン上で使用されるデジタル通貨(暗号資産・トークン)を利用して運用される金融サービスで「中央管理者が存在しない銀行」のようなものです。貯蓄・振込だけではなく、送金や投資などもインターネット上ですべておこなえます。
また、ブロックチェーンは送金料などの運用コストが低いことも、金融包摂と非常に相性がいいといえるでしょう。ブロックチェーン技術を用いたシステムには、中央集権的な管理者が存在しません。中央集権的な通常の銀行と比べると、中間マージンが非常に少なくなります。海外への送金には非常に有効な仕組みといえるでしょう。
金融包摂がもたらす3つのメリット
金融包摂をおこなえば個人だけではなく、企業や社会全体にメリットがあると考えられています。とくに、フィンテックを活用すれば世界中の人々が恩恵を受けることができるでしょう。ここでは、金融包摂がもたらすメリットを紹介します。
1.貧困を改善できる
低所得層は住まいや収入面などの影響で、銀行などの金融サービスにアクセスすることが非常に難しくなっています。身近にマネー教育をしてくれる人もいないため、思うように資産形成ができないのが現状です。
しかし、フィンテックによる金融サービスが簡単に受けられれば、インターネット環境があるだけで銀行にアクセスがしやすくなります。さらに金融サービスを受ければ、貯蓄や融資についての知識を学べるだけではなく、融資を受けて商業や教育へ投資が可能です。効率的なビジネスを展開できれば、極度の貧困を改善できるかもしれません。
2.質の高い教育が受けられる
貧困層・低所得層が簡単に金融サービスを使えるようになれば、教育を受ける機会が広がります。短期少額ローンや引き出し制限のある貯蓄(預金の引き出し制限があることで、計画的にお金を貯めることができます)、口座引き落としサービスなどが利用できるめです。
子どもへの教育投資は、地域や社会で経済が成長する要素のひとつです。
3.資金調達が困難な新興企業への融資(マイクロファイナンス)
貧困層や低所得者層の貧困緩和を目的としておこなわれる金融サービスをマイクロファイナンスといいます。マイクロファイナンスは、所得が少ない世代でも借入・返済できるように金融支援をおこなえることが特徴です。融資を受けて収入の安定に繋がれば、貧困からの脱出ができるかもしれません。
世界における金融包摂の事例
途上国・先進国問わず、金融包摂を必要としている人は一定数いるのが現実です。しかし、フィンテックを通じて活発な経済活動を促している国もあります。
事例1.インドにおけるフィンテック
世界の中でもフィンテックが著しく発展している国はインドです。インドは中国を超えて世界で最も人口が多い国になりました。しかし、国民ひとりあたりのGDPが低く、銀行口座が作れない人が多くいる状況でした。
しかし、フィンテック企業数が充実し、多くの人が金融サービスを受けられるようになりました。とくに、国民の個人情報をデジタル化した「アーダール(Aadhaar)」の浸透を進めてきたことが成功要因のひとつといえるでしょう。アーダールによる本人確認の仕組みが整備され、銀行口座の開設が容易になりました。
事例2.アフリカのフィンテック
2021年からアフリカではスマートフォンが浸透し、フィンテックが急速に普及しました。アフリカはSDGsに直結する社会的課題が多くあります。改善をおこなうために北米や欧州からスタートアップ企業への投資がおこなわれ、急激に成長しています。
フィンテックの事例では、ナイジェリアのFlutterwave(フラッターウェーブ)が有名です。アフリカ全土に決済ソリューションのサービスを展開し、中小企業を中心に融資をおこなっています。また、多くの米国企業への送金が可能になる決済API「Send App」を提供しています。
事例3.アメリカのフィンテック事情
アメリカでは2008年に発生したリーマンショック以降、クレジットカード発行に関しての審査が厳格になり発行が難しくなっています。そこで、金融サービスが利用できなくなった人に金融包摂する多くのフィンテック企業が登場しました。
たとえば、奨学金負債を抱える学生に奨学金より有利な条件で借り換えローンを提供するフィンテック企業SoFiがあります。
また、給料を前借したり、デビットカードのように使えるクレジットカードを発行したりする従来の銀行にはない機能をもった企業も存在するようになりました。
日本における金融包摂の事例
国内では金融包摂が無縁と考える人も少なくありません。しかし、高齢者・障がい者・在日外国人などには金融包摂が必要な場面が多々あります。ここでは、国内の金融包摂の事例を紹介します。
事例1.五常・アンド・カンパニー
「五常・アンド・カンパニー」は、世界の低所得者向けの金融包摂サービスを取り扱うホールディングスカンパニーです。マイクロファイナンスや低価格金融サービスを通じて、世界中の低所得者にアプローチをおこない持続可能な社会を目指します。
2023年3月時点ではアジア・アフリカの12カ国で事業を展開しています。グループ全体の従業員数は1万人以上で、顧客数は240万人とのことです。
事例2.グラミン日本
1983年にバングラデシュで創設された「グラミン銀行」のノウハウを生かして誕生したフィンテック企業が「グラミン日本」です。マイクロファイナンスや就労支援を通じて、シングルマザーを中心とした女性のために融資をおこなっています。
事例3.明治安田生命
明治安田生命は、企業ビジョンである「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社」の実現に向け、主に下記の金融包摂を実施しています。
- 高齢者に向けた取組み:高齢者向け専用ダイヤルの設置、電話音声明瞭器「サウンドアーチ」の設置、保険加入時に家族への契約内容説明など
- 障がい者に向けた取組み:耳や言葉が不自由な人向けの専用窓口、手話リレーサービス、代読・代筆・筆談対応など
『ブロックチェーンの活用事例を紹介!ビジネスで活用するメリットは?』では、フィンテックサービスを含むブロックチェーンの活用事例を紹介しているので、ぜひご覧ください。
MCB Web3カタログについて
MCB Web3カタログは、Web3領域におけるBtoBサービスを網羅的に検索・比較することができるカタログサイトです。MCB Web3カタログの会員(無料)になると、事業者向けのWeb3ソリューションに関する資料を個別もしくはカテゴリー別に請求できます。
- 「金融包摂施策のコンサルティングをフィンテックの専門家に依頼したい」
- 「フィンテックサービスにブロックチェーンを活用したい」
など、導入を検討中の事業者様にぴったりのサービスやソリューションが見つかるMCB Web3カタログを、ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

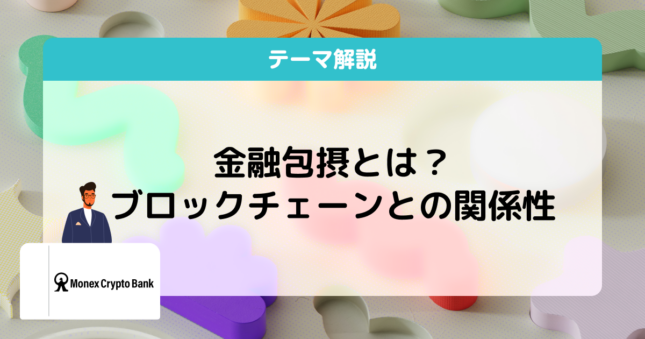

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




