ビットコインといえば「どこか危なそうなもの」「保有してみたいけれど、そもそもビットコインが何かわからない」という認識がいまだに強く根付いているのが現実です。そこで、本記事ではビットコインの定義や基本的な仕組みを解説していきます。
目次
ビットコインとは
ビットコインは、世界初のブロックチェーン技術を基盤とした暗号資産です。インターネット上で使える通貨ですが、国家や中央銀行などの中央集権型の管理者が存在しないことが特徴として挙げられます。
ビットコインのはじまりは、2008年10月です。正体不明の人物「サトシナカモト」が、インターネット上に論文「Bitcoin:A Peer-to-Peer Electronic Cash System(ビットコイン:ピア・ツー・ピアの電子現金システム)」を投稿しました。そして、論文を基にして開発者の手により作られたオープンソースのソフトウエアシステムがビットコインです。
ビットコインの仕組み・特徴
ビットコインの何が優れているのでしょうか。ここでは、ビットコインの仕組みや特徴を解説します。
世界中のユーザーが分散的にシステム管理している
ビットコインは、P2P(ピアー・ツー・ピアー)と呼ばれる人同士で形成されるネットワーク上に存在しています。従来のネットワークとは異なり、P2Pネットワークには中央集権的な管理者が存在していません。ユーザー同士が相互にビットコインの取引情報(トランザクション)を管理し、運営しています。
ユーザー同士が分散的にシステムを管理することで、ひとつのサーバーが故障したり、ハッキングを受けたりしてもシステムに影響がありません。中央集権的な方法を取る国家や中央銀行の仕組みとの大きな違いといえるでしょう。
ブロックチェーンを使用している
ネットワーク上のデジタル通貨として存在しているビットコインは、「ブロックチェーン」と呼ばれる技術を利用しています。ブロックチェーンとは「分散型台帳技術」とも呼ばれ、ビットコインのトランザクションを記録します。
トランザクションの記録データはブロック(箱)ごとに分けて保存し、ブロック同士をチェーン(鎖)で繋いだ構造をしているためブロックチェーンと呼ばれています。各ブロックは複雑な暗号を用いてトランザクションを保存・管理します。さらに、暗号は前後のブロックで密接な関係があります。セキュリティが非常に高く、情報の改ざんやシステムの不正利用が容易にできません。
ブロックチェーンは複雑な仕組みをしていますが、家計簿や会計帳簿みたいなものと考えても差し支えありません。ただし、管理者が個人・会社・銀行・国家ではなく、ユーザー同士で分散管理をしていることを覚えておきましょう。
発行枚数が決まっている
ビットコインの発行枚数は、2,100万枚と決められています。無計画に発行してしまえば需要よりも供給量が増えてしまい、ビットコインの価値を急落させてしまうでしょう。
また、ビットコインは増加量をコントロールして、発行枚数を管理しています。ビットコインが発行されるタイミングは、新しいブロックが生み出される約10分に1回です。2025年1月時点で発行枚数は約1,981万枚で、全体の約94%となりました。発行枚数が上限に達するのは2140年と予想されています。
インターネットにつながっていれば誰でも使える
ビットコインはP2Pネットワーク上に存在しているため、ネットワークに接続できるパソコン・スマホ・タブレットなどがあれば誰でも使えます。ビットコイン専用の口座(ウォレット)を開設し、専用アプリに二次元コードを読み取らせるだけで決済が可能です。従来のECサイトでのインターネット決済や、バーコード・二次元コード決済などと同じように扱えます。
家電量販店「ビックカメラ」ではビットコイン決済を導入しており、国内の店舗で幅広く利用可能です。ビットコイン決済に対応した店舗を地図上で探せる「BTC Map」のようなアプリもローンチされているため、必要があれば使ってみましょう。
ビットコインと電子マネーの違い
ビットコインと電子マネーは似ていますが、全く異なる特徴を持ちます。電子マネーの身近な例でいえば「Suica」のような交通系プリペイドカードが挙げられます。現金先払いで運賃を払込み、必要なときに決済をおこないます。超高速で決済がおこなえることが特徴でしょう。
一方、ビットコインはウォレットに入っている資産で直接取引をおこないます。電子マネーのようなチャージは必要なく、そのまま決済が可能です。決済速度は電子マネーには劣りますが、ビットコイン決済に対応している店舗であれば世界中どこでも利用できます。
また、カード・決済を管理している機関にも違いがあります。交通系プリペイドカードなどには鉄道会社・運営会社などの中央集権的な機関が存在しますが、ビットコインには特定の管理者が存在しません。
ビットコインのマイニングの仕組み
マイニングとは、ビットコインのトランザクションを検証・承認する作業です。膨大な数式を解く作業が「採掘」に似ていることからマイニングと呼ばれ、マイニングをおこなう人をマイナー(採掘者)といいます。マイニングの種類は下記の3種類です。
<マイニングの種類>
- ソロマイニング:個人でマイニングをおこなう方法
- プールマイニング:複数の人と協力してマイニングをおこなう方法
- クラウドマイニング:マイニングをおこなっている団体に投資して利益を得る方法
マイニングでは「ナンス値」と呼ばれる特定の値を見つけることが目的です。ナンス値は「number used once:一度だけ使われる数」の略で、使い捨ての32ビットの値です。膨大な計算によって導き出されたナンス値は他のノード(コンピューター端末)によって検算され、正しければ新たなブロックが生成されます。
ビットコインの設計上、生成可能なブロック数は692万9,999個です。ブロックチェーンが長くなるほど暗号が長くなり、ナンス値を導き出すのが困難になります。難易度が上がる理由は、ビットコインの過剰供給によって、価値を落とさないインフレ対策といわれています。
マイニングでビットコインが増える仕組み
ビットコインでは、マイニングで報酬が支払われる仕組みを採用しています。報酬を受け取れるのは、最初にナンス値を発見したノードのみです。2024年11月時点では「3.125BTC=2,600万円程度」報酬が支払われます。
現在では、専用の超高性能ACICなどを多数導入して膨大な電気代を消費しなければ、マイニングで報酬を得るのは難しいでしょう。個人レベルで報酬を得るのは現実的ではなく、企業レベルでの作業になっています。しかし、個人マイナーでもブロック生成に成功した事例もあるため、個人マイナーが「絶対に企業には勝てない」と断言はできません。
コンセンサスアルゴリズムとは
ブロックチェーンでブロックを追加する際に、ノード間で計算結果が正しいかどうかを検証・合意する方法を「コンセンサスアルゴリズム」といいます。
ビットコインでは「プルーフ・オブ・ワーク(Proof of Work:PoW)」というコンセンサスアルゴリズムを採用しています。PoWを簡単に説明すれば、膨大な計算(Work)をしたノードに報酬を与えるという仕組みです。
PoWのメリットは、膨大な計算を解かなければブロックを生成できないということでしょう。改ざん・不正利用対策に非常に有効に働きます。
たとえば、ブロックチェーンの改ざんをおこなう場合には、前後やそれ以前の情報をすべて書き換えないといけません。PoWを採用している場合には、ひとつのブロックを改ざんするにしても膨大な計算が必要です。善意をもったノードに気づかれる前に、すべて情報を変更するには現在のコンピューター技術では不可能だといわれています。
一方で、PoWは消費電力が大きいといった問題もあり、PoSや他のコンセンサスアルゴリズムも開発されています。
51%攻撃とは
「51%攻撃」とは、ブロックチェーンネットワークの計算能力(ハッシュレート)の過半数を単一の主体が支配することで可能となる攻撃手法です。この攻撃が成功すると、攻撃者は以下のような操作が可能になります。
- 同じ暗号資産の二重支払い
- 直近の取引履歴の書き換え
- 新規取引の承認プロセスの妨害
ただし、この攻撃には膨大なコストと技術的リソースが必要となり、大規模なブロックチェーンネットワーク(ビットコインなど)では実行が極めて困難です。また、攻撃が成功しても過去の取引履歴を完全に書き換えることはできません。
ビットコインの半減期とは
「ビットコインの半減期」とは、マイニングでのビットコインの報酬が半減になるタイミングを指します。ビットコインの供給量を調整してインフレを抑制するために設定されました。
ビットコインの半減期は、21万ブロックごとに報酬が半分になるようにプログラムされています。1ブロックの生成時間には10分かかり、半減期は4年に一度発生します。過去に発生した半減期は下記です。
表:過去4回の半減期
| 年 | 月 | ブロック報酬 |
|---|---|---|
| 2012年 | 11月 | 25BTC |
| 2016年 | 7月 | 12.5BTC |
| 2020年 | 5月 | 6.25BTC |
| 2024年 | 4月 | 3.125BTC |
ビットコインの仕組みに関するよくある質問
ビットコインの送金手数料はいくら?
ビットコインは、暗号資産取引所やウォレットアプリなどを利用して送金できます。送金手数料は暗号資産取引所などによって異なり、代表的な取引所の手数料は下記です。
表:代表的な取引所の送金手数料/2024年9月現在
| 取引所 | ビットコイン送金手数料 |
|---|---|
| GMOコイン | 無料 |
| BITPOINT | 無料 |
| SBI VCトレード | 無料 |
| bitFlyer | 0.0004BTC |
| Coincheck | 0.0005BTC |
| BitTrade | 0.0005BTC |
| Cointrade | 0.0005BTC |
| bitbank | 0.0006BTC |
| LINE BITMAX | 0.001BTC |
| OKCoinJapan | 0.0005~0.02BTC |
| Zaif | 0.0001~0.01BTC |
※2024年11月時点
国際送金おける手数料が安価なビットコイン
暗号資産を使った国際送金は、従来の銀行送金と比べていくつかの大きな利点があります。
1. 送金コストの削減
銀行間手数料が不要 – 為替手数料が発生しない
中間業者を介さないため余分な費用が少ない
2. 送金時間の短縮
24時間365日、即時送金が可能
銀行の営業時間に縛られない – 国際送金でも数分から数十分で完了
ビットコインはハッキングされる?
ブロックチェーンをハッキングしてブロックの内容を改ざんするのは、現実的に不可能とされています。ただ、暗号資産取引所がサイバー攻撃の対象になった事件は少なくありません。ハッキングを受けて多額のビットコインが流出してしまったケースは多く、各国で何十億円相当のビットコインが流出する事件が起きています。
これらの事件の多くに共通する脆弱性は、「ホットウォレット」の利用でした。ホットウォレットはインターネットに接続された状態で暗号資産を管理するため、ハッキングや不正アクセスのリスクが残ります。現在では、セキュリティを強化したり、コールドウォレットを採用したりする取引所が増えています。
ビットコインに税金はかかる?
トレードなどの取引で発生した利益は課税の対象です。確定申告で納税をする義務があります。
課税区分は「雑所得」に分類され、累進課税制度により5%から45%の所得税が課されます。原則としてビットコインを保有しているだけでは課税の対象になりませんが、主に下記の場合に課税対象です。
<課税対象になるケース>
- ビットコインを売却した場合
- 含み益が出た状態でビットコイン決済を利用した場合
- ビットコインで他の暗号資産を購入した場合
- マイニングでビットコインを取得した場合
国内では過去にも申告忘れが発覚し、多額の追徴課税を受けた事例も多くあります。「確定申告しなくてもバレないだろう」と安易に考えていると、自己破産や任意整理に追い込まれるケースがあるため、注意してください。
まとめ
ビットコインは、Web3の根幹となるブロックチェーンや暗号資産の地位を確立しました。PoWという仕組みを用いて、自律分散的にビットコインブロックチェーンが稼働し続けている様子は、Web3の成功例の代表例だといっても過言ではありません。
Web3を理解するうえで、ビットコインの理解は必須ともいえる知識になるため、しっかりと覚えておきましょう。
また、弊社マネックスクリプトバンク株式会社では、Web3領域におけるBtoBサービスを比較・検討することができるMCB Web3カタログを提供しています。
無料の会員となることで、事業者向けのWeb3ソリューション関連資料を請求することができます。ぜひご活用ください。
MCB Web3カタログへ掲載してみませんか?掲載社数は約50社、国内随一のWeb3 × BtoBサービスの検索・比較サイトです。

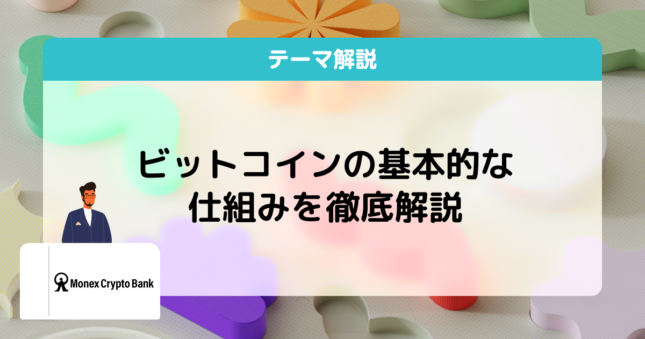

 web3ニュースレター
web3ニュースレター




